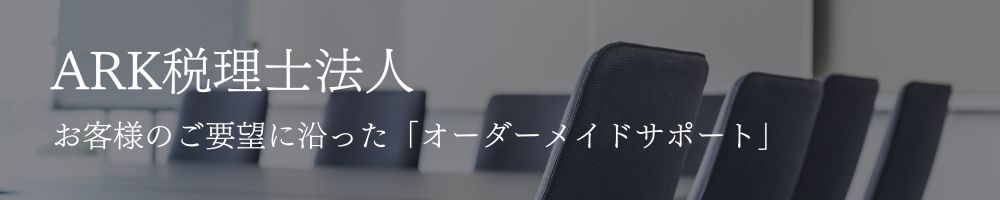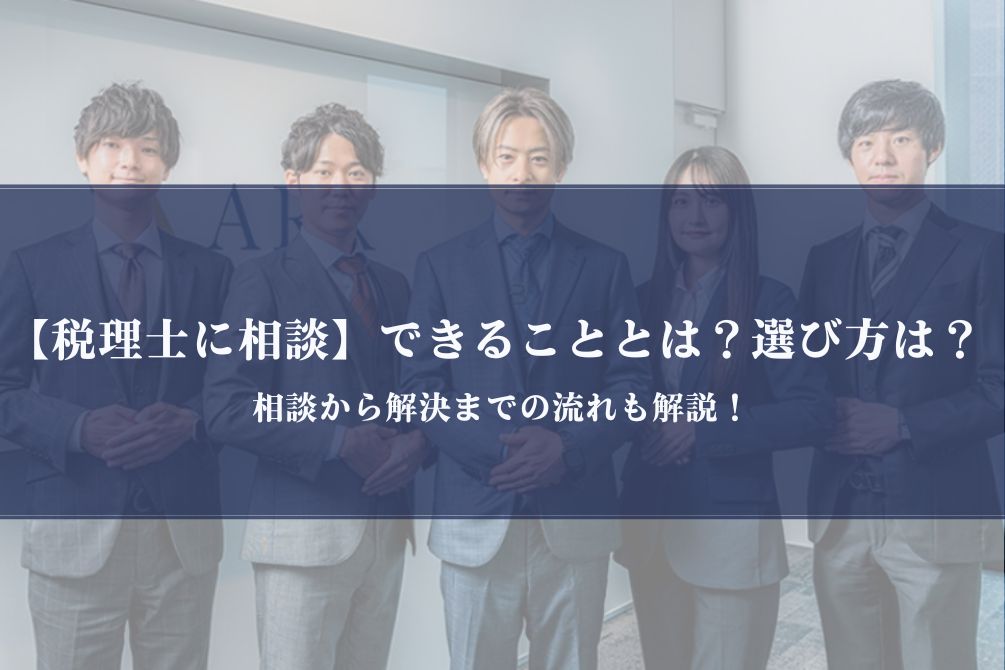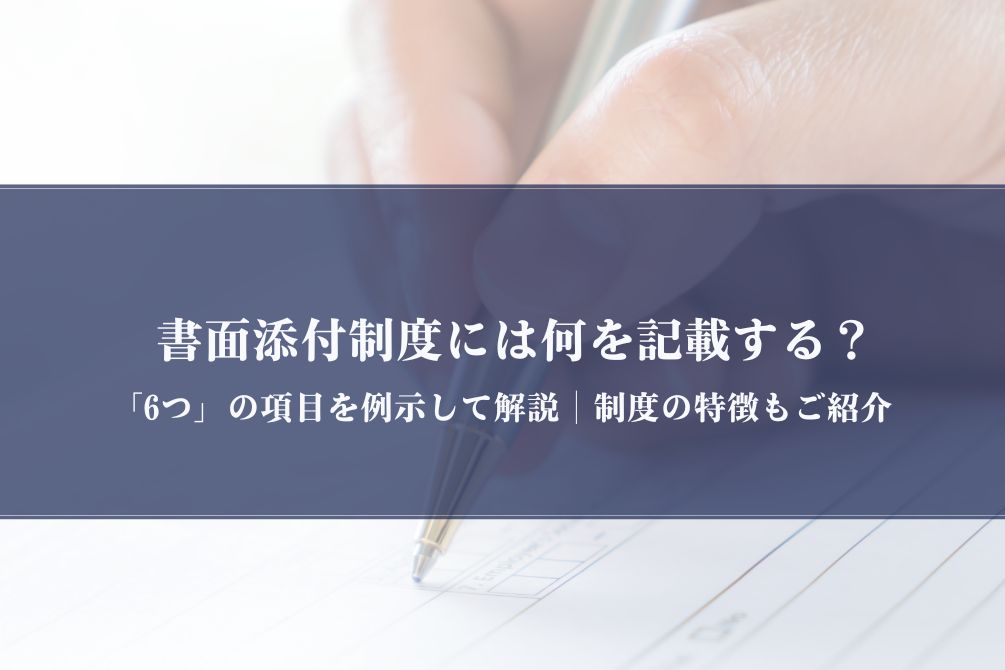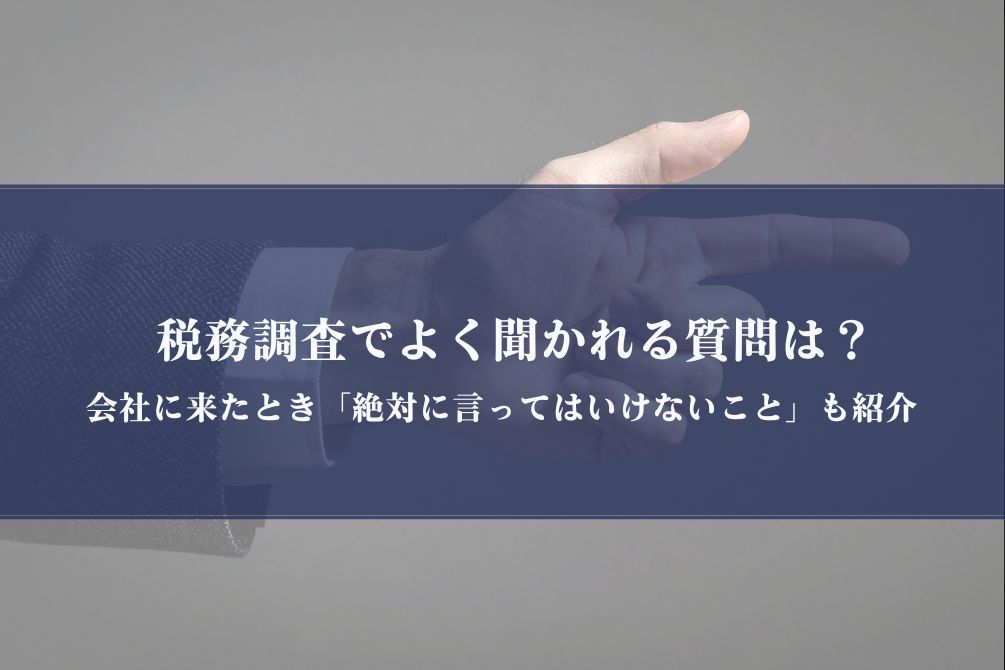会社の資金繰りを改善する『お金がかからない』節税対策3選、注意点も解説
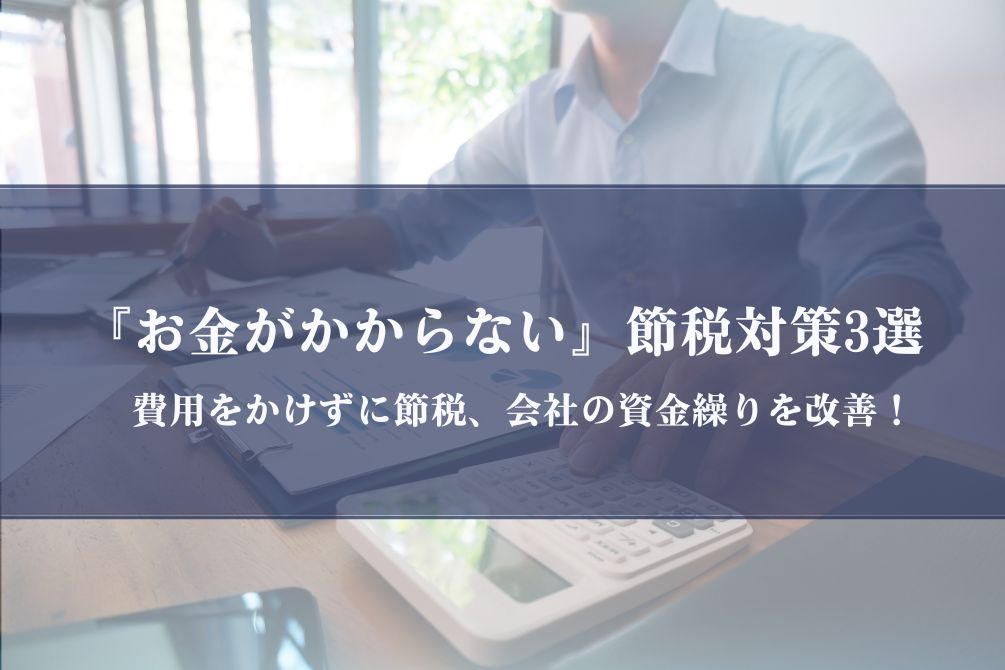
会社の節税対策を考えている経営者は多いでしょう。
中でも資金繰りを圧迫せずに実践できる「お金がかからない節税」は、特に注目されるテーマです。
本記事では、そもそも節税対策とは何かをわかりやすく解説したうえで、中小企業が活用しやすい具体的な節税制度を3つ紹介します。
制度利用時に注意するべきポイントもご紹介しますので、会社の税金を抑えたいと考えている経営者や経理担当の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも「節税対策」とは?
節税対策とは、法律に則って税金の負担を軽くするための取り組みです。
経費の使い方や税制優遇制度の活用などにより、支払う税金を合法的に抑える方法を指します。
節税・脱税・租税回避の違い
税金に関する対策には、次の3つの考え方があります。
- 節税:合法的に税負担を減らす(例:税額控除の活用)
- 脱税:法律違反で税を逃れる(例:売上の隠蔽)
- 租税回避:法の抜け穴を使って税を逃れる(否認リスクあり)
同じ「税金を減らす行為」でも、法を犯すものから適切に税負担を軽くするものまで、多様な方法があります。
おすすめは節税(合法に税金額を節約)
税金対策として最も安心で効果的な方法は、正しい知識に基づく「節税」です。
脱税は法律違反で、税務調査で発覚すれば追徴課税や罰金、場合によっては刑事罰の対象にもなります。
また、租税回避も形式的には合法でも、意図的と判断されれば否認(経費として認められないこと)される可能性があり、結果的に損失につながるリスクもあります。
だからこそ、合法的かつ戦略的に税負担を減らせる節税こそが、会社を守る最適な手段といえるのです。
▶関連コラム:【明日 税務調査が来たら…】税理士が教える税務調査が来た時やること・流れを徹底解説!

橋場先生
「どの制度が使える?」「手続きが不安…」という方は、税務の実績が豊富なARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
節税と経営支援を両立する“伴走型サポート”で、最適な節税対策をご提案します。
お金がかからない!おすすめの節税対策3選
「節税=出費が必要」と思っていませんか?
たとえば、「倒産防止共済」や「小規模企業共済」といった制度は有効な節税対策になりますが、掛け金を支払う必要があり資金に余裕がないと難しいと感じる方も少なくありません。
▶関連コラム:経営セーフティ共済(倒産防止共済)を利用した駆け込み節税とは?決算期に加入する注意点、制度の概要も紹介
▶関連コラム:【個人事業主の厚生年金の代わり】小規模企業共済、4つのメリット・2つのデメリットを解説
一方で、大金を使わずに活用できる税制優遇制度もあります。
具体的に、中小企業におすすめの、コストを抑えて税金を減らせる制度を3つご紹介します。
中小企業投資促進税制:設備投資で節税
本制度は、一定額以上の設備投資を行うことで、法人税の税額控除(最大7%)または特別償却(30%)が受けられる制度です。
対象となるのは、機械や装置(160万円以上)、測定工具、ソフトウェア、一定の貨物自動車などです。
通常の経費処理に加え、税金そのものを減らせるため資金繰りにも効果的です。
事前準備が必要ですので、計画的な活用がカギとなります。
中小企業経営強化税制:経営力強化で節税
本制度では、経営力の向上につながる設備投資に対し、即時償却または最大10%の税額控除を選択できます(※一部企業は7%)。
たとえば、社内の食堂や休憩室、テレワーク設備、勤怠管理システムなどが対象となります。
従業員の働きやすさや業務効率の向上も図れるため、福利厚生と節税を同時に実現できる制度です。
所得拡大促進税制(賃上げ促進税制):給与アップで節税
本制度は、従業員の給与を一定以上アップした場合、その増加額の一部を法人税(または所得税)から控除できる制度です。
物価高の影響を受ける今、従業員満足度を高めながら節税できるメリットがあります。
賃上げを検討している企業にとっては、経費+税額控除で“二重の効果”が得られる制度としておすすめです。
▶関連コラム:【中小企業必見】実際に従業員の給料を月10万円上げるとどうなる?賃上げ促進税制について
節税制度活用の注意点
節税制度は魅力的ですが、使い方を誤ると適用されないリスクもあります。
正しく活用するためには、事前の準備や税制の仕組みへの理解が不可欠です。
各種税制適用には事前準備と専門知識が必須
多くの節税制度は、設備の取得前や賃上げ前に届け出や申請が必要です。
また、制度によっては「取得日」「使用開始日」「対象要件」など細かな条件が定められており、一つでも漏れると適用されないケースもあります。
申請書類の作成や証拠資料の整備も求められるため、制度を正確に理解し、計画的に準備することが重要です。
自己判断による申請は否認につながる恐れも
制度の概要だけを見て自己判断で進めることも危険です。
書類の形式ミスや誤った要件解釈により、税務署に否認されるケースも少なくありません。
特に節税目的が強すぎる申請は「租税回避」と判断される可能性もあるため注意が必要です。
制度をフルに活用し、かつリスクを避けるためには、経験豊富な税理士に相談することが安全かつ確実な方法です。

橋場先生
制度を正しく活用するには、専門知識と申請実務に精通した税理士のサポートが不可欠です。
ARK税理士法人なら、豊富な実績と最新の税制知識をもとに、最適な節税プランをご提案します。
安心して制度を使いたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
節税対策は、会社の資金繰りを改善し、経営を安定させる重要な手段です。
中でも、「お金をかけずに税金を減らせる制度」は、積極的に活用するべき価値があります。
ただし、制度ごとに要件や申請のタイミングが異なるため、専門家のサポートが欠かせません。
ARK税理士法人では、節税制度の活用から経営改善までトータルでサポートしています。
「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.