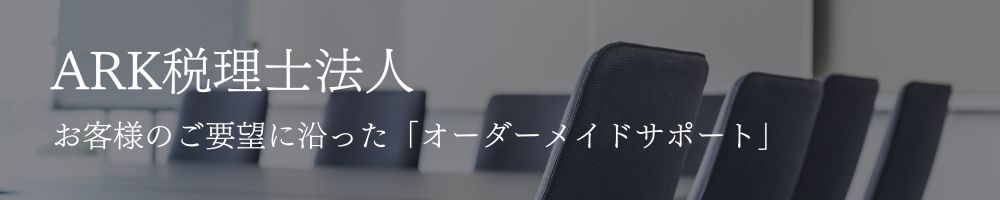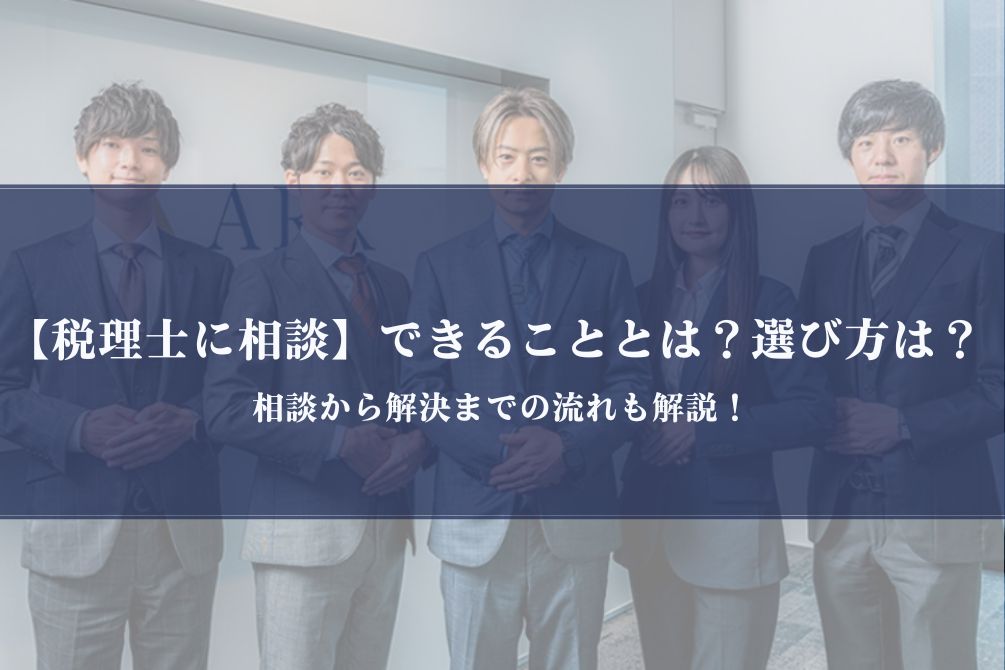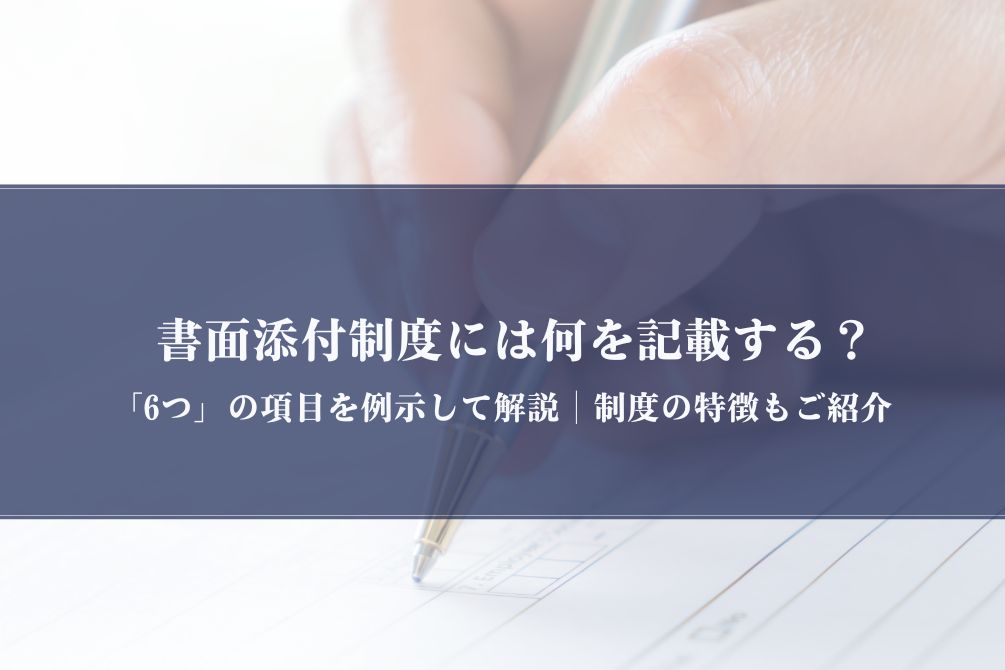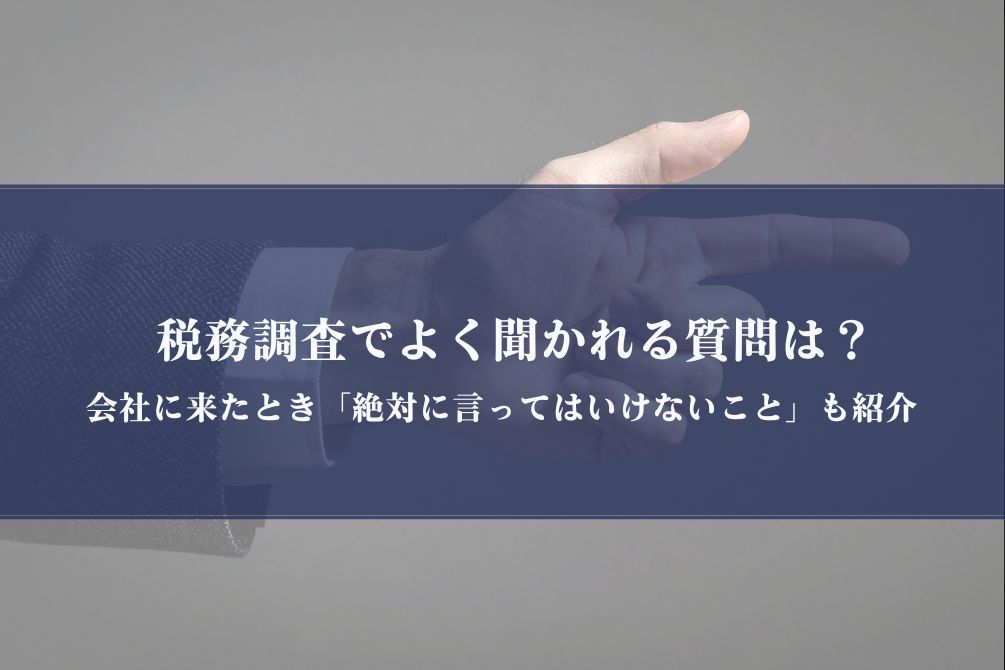【確定申告】無申告の時効は何年?「バレた」場合の罰則、ダメージを最小化する方法も解説
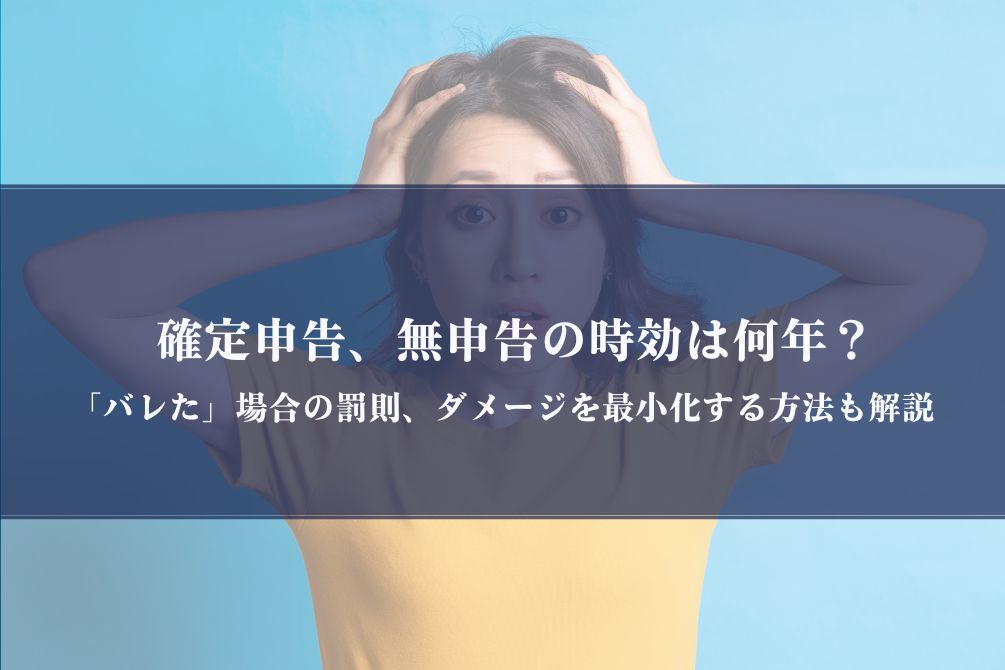
「確定申告をしないまま数年が経過してしまった」
そんなとき、頭をよぎるのは「税金にも時効があるって本当?」という疑問です。
実は、税金にも“時効”は存在します。
その一方で、「バレて、重いペナルティ(税金)が課された」というケースも後を絶ちません。
本記事では、無申告に関する時効の基本から「3年、5年、7年」といった年数の違い、バレるリスクや罰則の内容、損をしないための対応方法まで、税理士がわかりやすく解説します。
目次
結論:無申告の時効は「調査3年、原則5年、悪質7年」
無申告の税金にも「時効」はあります。
ただし、その期間は一律ではなく、状況により3年、5年、7年に分かれます。
- 税務調査で一般的に調査対象となる期間:3年
- 国税の徴収権の消滅時効期間:原則5年
- 仮装、隠ぺいがあるなど悪質な場合:最長7年
「いつまで遡って課税されるのか」は、申告義務を怠った状況や行為の内容によって変わります。
▶関連コラム:【明日 税務調査が来たら…】税理士が教える税務調査が来た時やること・流れを徹底解説!
そもそも「時効」とは?
税務における「時効」とは、税務署が税金を課すことができる期限や、納税者から税金を徴収できる期限を指します。
この期間を過ぎると、原則として税金の請求や徴収はできなくなります。
知っておきたい「起算点、中断と停止」
時効には、「いつからカウントするのか(起算点)」と、「どんなときに時効がリセットされるのか(中断、停止)」という重要な考え方がありますので解説します。
起算点:時効の到来日を数え始める日
- 法定申告期限の翌日からスタート
- 例:2025年分の申告期限(2026年3月15日)を過ぎた場合…起算点は2025年3月16日
時効の中断:特定のイベントがあった場合に、時効のカウントがリセットされる
- 税務署からの「督促状」や「催告書」
- 「税務調査の着手」や「更正処分の通知」
- 差押、捜査などの執行手続き など
時効の停止:特定のイベントがあった場合に、時効のカウントが一時的に停止される
- 納税者が国外に出ていて調査できないとき
- 納税者が死亡して、相続未確定の場合
- 自然災害などで申告や調査が困難なとき など

橋場先生
「そろそろマズいかも…」「自分のケースは時効になるのか?」
そんな不安をお持ちの方は、まずは専門家に状況をお話しください。
ARK税理士法人では、無申告や期限後申告に関するサポートを多数手がけており、調査対応やペナルティ軽減策のご相談も可能です。
“今できる最善の一手”を一緒に探しましょう。
無申告が「バレた」場合の罰則とは?
無申告の状態が発覚すると、本来納めるべき税金に加え、加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
状況によっては、重加算税の対象になることもあり、放置していた期間が長いほど、負担は大きくなります。
- 無申告加算税:確定申告を期限までにしなかった場合に課される税金(原則:納付すべき税額の15%)
- 重加算税(悪質な場合):意図的な隠ぺいや仮装行為があると認定された場合(税額の35〜40%のペナルティ)
- 延滞税:本来納付すべき期限を過ぎてからの期間に応じて加算される税金(7.3%、2か月目以降14.6%)
- 青色申告の取消:無申告が続くと、青色申告の承認が取り消される場合も
税務署からの指摘を受けてからの対応では損失が大きくなりがちですので、少しでも早く自主的な申告を行うことが負担を軽減するカギになります。
▶関連コラム:税務調査が不安な方へ│対象になる条件や経費の内容、今からできる対策も解説
時効がバレる経路とは?
「無申告、1~2年経過したし、私はバレないのでは?」
このように思っていても、税務署には無申告者を把握する様々な情報ルートがあります。
以下のとおり思わぬ形で発覚するケースも多く、“気づかれずに逃げ切れる”可能性は低いと言えるでしょう。
- マイナンバーと銀行口座の紐付け:取引履歴や残高を通じて申告漏れが判明
- 反面調査(取引先や関係者への調査):元請け、仕入先の帳簿の「支払記録」から芋づる式に発覚
- SNS、ネット販売、副業プラットフォームなどの情報:発信情報や売買履歴から発覚
- AIによる申告漏れの選定、監視体制:AI分析を活用した無申告リスクのある納税者の確認
「まさか自分が」と思っていても、数年越しで連絡が来ることは珍しくありません。
発覚してから慌てるより、早めに正しい対応を取ることが何よりのリスク対策となります。
無申告の罰則を最小化する方法
無申告に気づいた場合でも、すぐに重い罰則が課されるとは限りません。
大切なことは、税務署からの連絡や調査が入る「前に」、自主的に期限後申告を行うことです。
以下のとおり適切な対処によって、加算税の軽減や青色申告の継続が認められる場合があります。
- 加算税の軽減: 税務署の指摘前に自主的に申告すれば、無申告加算税が原則5%に軽減
- 延滞税の抑制: 早めの申告、納付で、延滞税(利息的な税負担)を最小限に
- 修正申告でペナルティ回避: 誤りの修正申告で加算税の回避
- 還付の可能性: 税金を多く納めていた場合には、「更正の請求」で支払いすぎた税金が戻る場合も

橋場先生
無申告であっても、「まだ何も来ていない」今のうちに行動すれば、税務署からの評価が変わり、ペナルティが軽減される可能性が十分あります。
「どこから手をつければいいかわからない」「帳簿や資料も整理できていない」
こうした不安を感じている方も、お気軽にARK税理士法人にご相談ください。
まとめ
税金の無申告には時効があるものの、それが確実に成立するとは限らないのが現実です。
むしろ、知らぬ間にバレて重い罰則が課されるケースが少なくありません。
税務署からの通知が届く前に自主的に期限後申告を行うことで、加算税や延滞税を軽減できる可能性があります。
今すぐに税務についての問題を全て解決する必要はありません。
まずは正しい情報を知り、できることから動き出すことが大切です。
ARK税理士法人では、期限後申告のサポートやペナルティ軽減の対応を通じて、経済的、精神的な負担を少しでも軽くできるようサポートしています。
「相談してよかった」と思っていただけるご対応をお約束しますので、お気軽にご連絡ください。
Contact
We will support you like a butler.