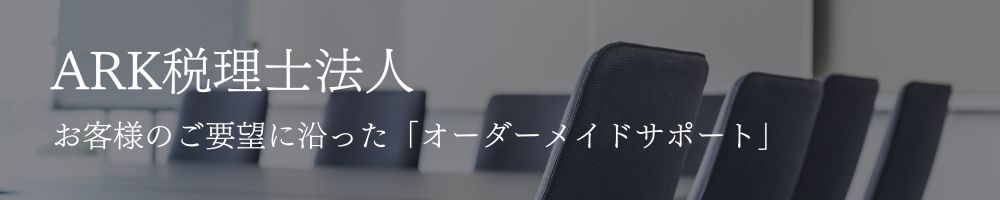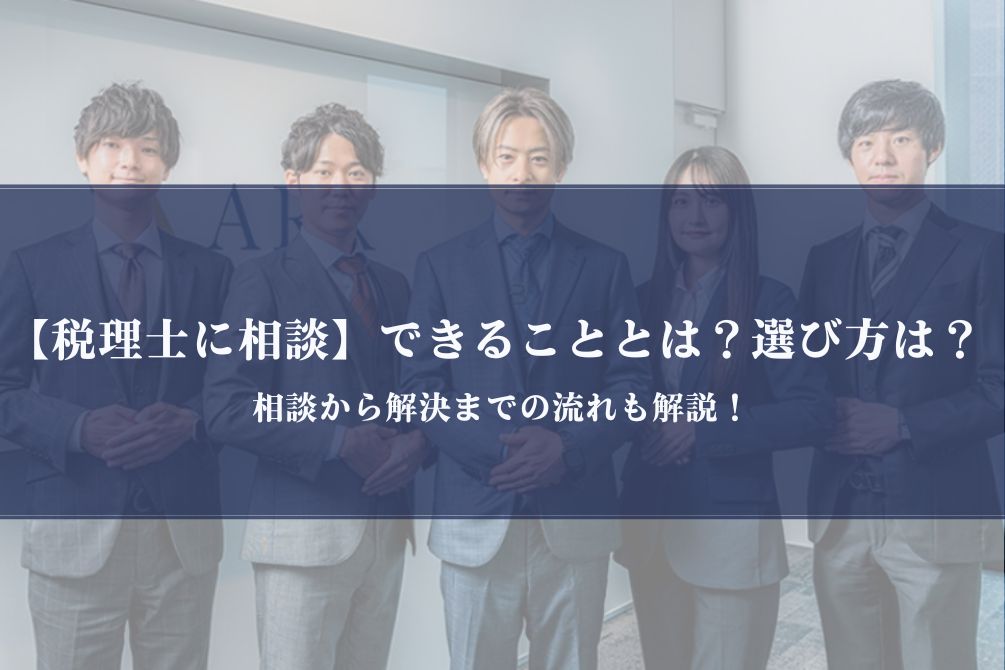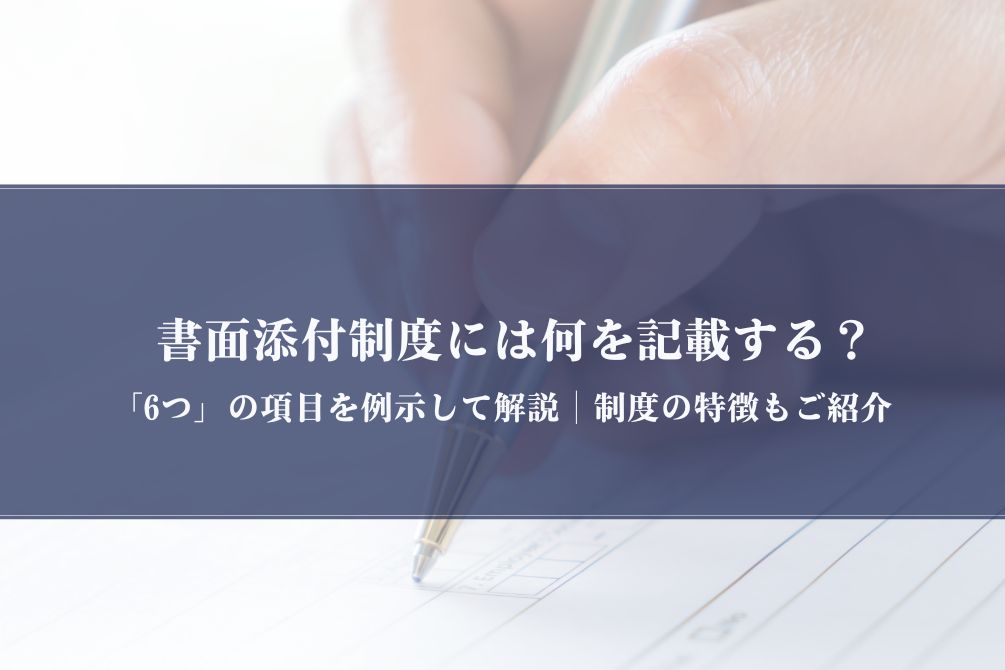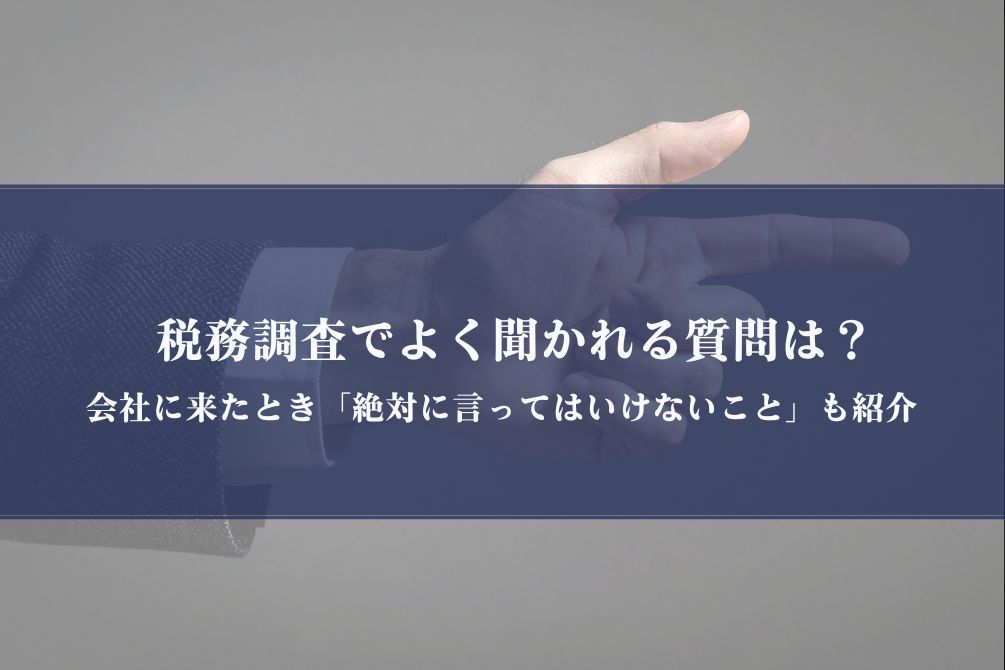税務調査で追徴課税を受けたらどうする?追徴課税の種類や金額、払えない場合の対処法など分かりやすく解説
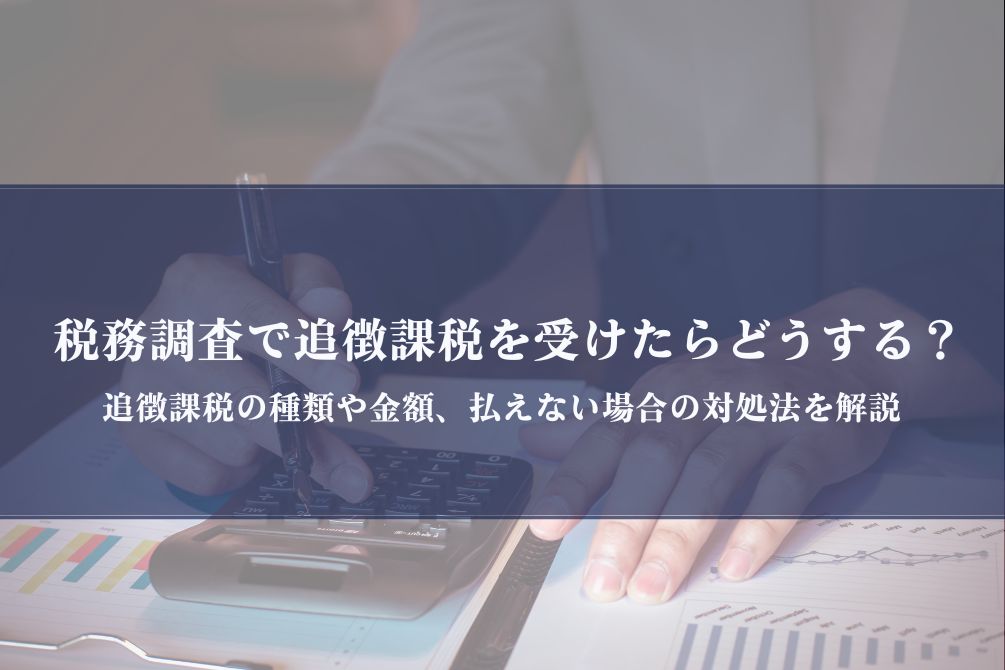
確定申告など、納税に関する申告内容を税務署や国税局が調査する「税務調査」。
調査の結果、追徴課税(申告内容に誤り、漏れがあった場合に課される追加の税金)を受けた方の例を聞くと、不安を感じる方は多いものです。
そこで本記事では、追徴課税の仕組みから金額の目安、もしもの「払えない」事態に利用できる救済制度まで詳しく解説します。
目次
追徴課税とは?税務調査で受けるペナルティ
追徴課税とは、確定申告の内容などについて精査を受ける「税務調査」を受けた結果、申告漏れや計上ミスが見つかった場合に、追加で課される税金を指します。
たとえば、経費の計上を誤っていた場合や売上を申告し忘れていた場合などが該当します。
▶関連コラム:【明日 税務調査が来たら…】税理士が教える税務調査が来た時やること・流れを徹底解説!
本来納めるべき税に加えて徴収される「ペナルティ税」
正しい納税額との差額を「不足分の税金」として支払った上で、さらに罰則的に支払うこととなる、追徴課税は「ペナルティ」の意味合いを持つ税金です。
追徴課税は単なる罰金ではなく、あくまで「正しい税金を支払ってもらう」ことを目的にした制度ですが、金額が大きくなるケースも多く、事業者にとっては避けたいイベントといえます。
追徴課税の主な種類をご紹介
税務調査の結果課される税金には、以下のとおり複数の種類があります。
- 過少申告加算税:申告額が少なかった場合に課される税(10〜15%)
- 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合(15〜30%)
- 重加算税:意図的な隠蔽や仮装があった場合(35〜40%)
- 不納付加算税:源泉徴収した所得税などを納めなかった場合(10%)
- 延滞税:納付が遅れた日数に応じて課される「利息のような税金」
このように追徴課税は種類ごとに税率が異なりますので、「違反の種類と税率」をおおまかに把握して、重加算税のように重いペナルティを避ける意識が大切です。
追徴課税はいくら取られる?金額の目安と時効期間
実際に追徴課税を受けてしまった場合、具体的にどの程度の税金を支払う必要があるのでしょうか。
金額の目安と、知っておきたい「時効」についてお伝えします。
加算税率の目安(10〜40%)と延滞税の仕組み
追徴課税の金額は「不足した税額 × 加算税率」で算出されます。
また、加算税率は申告内容や税額の修正タイミングによって異なり、「悪質性が高い」と判断されるほど高くなります。
たとえば申告漏れで50万円の所得税が追加で発生した場合を考えましょう。
- 期限内に自主的に修正申告をした場合:約5万円(過少申告加算税、加算税率10%)
- 調査で指摘を受けた場合:約7.5万円(無申告加算税、加算税率15%)
- 故意の隠蔽があった場合:約20万円(無申告加算税、加算税率40%)
さらに、納付が遅れた日数に応じて延滞税も加算されます。
延滞税は原則年7.3%、または14.6%(一定期間経過後に変更)で計算され、たとえば100万円を1年間放置すると、延滞税だけで10万円を超える追加負担が必要になる計算です。
このように追徴課税は「遅れるほど増える」仕組みですので、自主的な修正や早期の納付が、結果的に支払う税金を抑えるポイントになります。
税務調査の対象期間(通常3年・重加算時5〜7年)
税務調査では、原則として過去3年分の申告内容が調査の対象となります。
ただし、以下のようなケースでは期間が延長される点に注意が必要です。
- 重加算税(悪質な隠蔽など)の対象:最大で5年
- 国外取引、特定事案など重大な問題:最大で7年

橋場先生
税務調査は過去にさかのぼって修正が必要になるケースもありますので、日常的に帳簿や領収書を正確に保管することが重要といえます。
また、日々の記帳を正確にすることが最大の対策になりますので、ご自身や経理の帳簿付けに不安を感じている方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
税務調査、払えないときの救済制度と注意点
税務調査で追徴課税を受けた場合、「払えない」といったケースもありえます。
こうした場合に救済制度はないのでしょうか。
「納税の猶予」「換価の猶予」で納税の延期が可能
追徴課税の金額が大きく、一度に支払えない場合は「納税の猶予」または「換価の猶予」という制度を利用できます。
- 納税の猶予:資金繰りの悪化など、納付が困難な場合に適用
- 換価の猶予:財産差押えを一時的に免れ、納付計画に従い返済する制度
要件を満たせば最長1年、支払いの延長措置を受けることが可能となります。
追徴課税の放置によるリスクと注意点
追徴課税を放置すると、次のようなリスクが順番に発生することとなりますので、把握しておきましょう。
- 財産の差押え:預金や不動産、車両などを対象に強制的に財産を没収される
- 自己破産時の免責なし:追徴課税は「特別な債権」で、破産後も支払い義務が残る
- 信用低下リスク:督促や差押えが公になることで、金融機関や取引先からの信用喪失に

橋場先生
税務調査で追徴課税を受けて支払いが厳しい場合にも、専門家への相談は有効です。
ARK税理士法人では、納税猶予、換価の猶予の申請支援、また支払い後の経営計画まで一括してサポート致します。
無理のない納付と再発防止を両立する方法を、経験豊富な税理士がご案内しますので、お気軽にご相談ください。
追徴課税を減らす、防ぐための実務対応
紹介したように、追徴課税は経営に影響を与えるほどのペナルティで、避けるべきイベントですが、税務調査で誤りを指摘された場合でも、修正申告により加算税を軽減する、内容に納得できないときは不服申立てや再調査請求を行うといった手続きも可能です。
合わせて、日頃から以下のとおり対応を徹底することで、調査の際に指摘を受ける確率を減らせます。
- 領収書や請求書は原本を5年以上保管
- 支出にメモを添付するなど、経費計上の根拠を整理
- 税理士が精査し”お墨付き”を出す「書面添付制度」を利用
追徴課税を受けた場合に備え、また受けないようにする対策を取り、多額のペナルティを支払うリスクを避けましょう。
▶関連コラム:税務調査が不安な方へ│対象になる条件や経費の内容、今からできる対策も解説
まとめ│追徴課税回避は早めの対応が大切
▶関連コラム:ココが違う!ARK税理士事務所と一般的な税理士事務所│5つの強み、サポートの実例を紹介
税務調査で指摘され追徴課税を受けると、不安や焦りを感じるのは自然なことです。
しかし、放置すれば延滞税の増加や信用への影響など、負担は確実に大きくなります。
ARK税理士法人では、豊富な経験をもとに、追徴課税に対して「今できる最善の一手」を丁寧にご提案します。
修正申告や納税猶予の申請サポート、税務署との交渉なども一括して対応致します。
不安を安心に変える第一歩として、早めに専門家へご相談ください。
問題を先延ばしにせず行動することが、最も確実なリスク回避につながります。
Contact
We will support you like a butler.