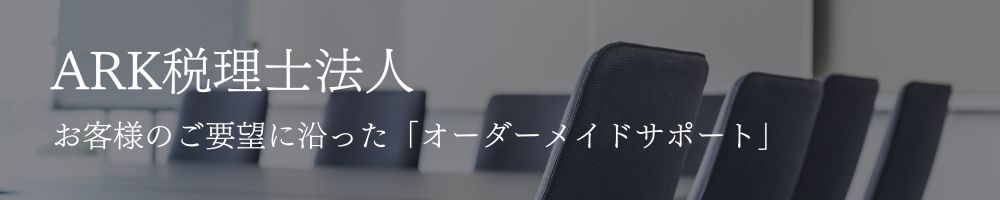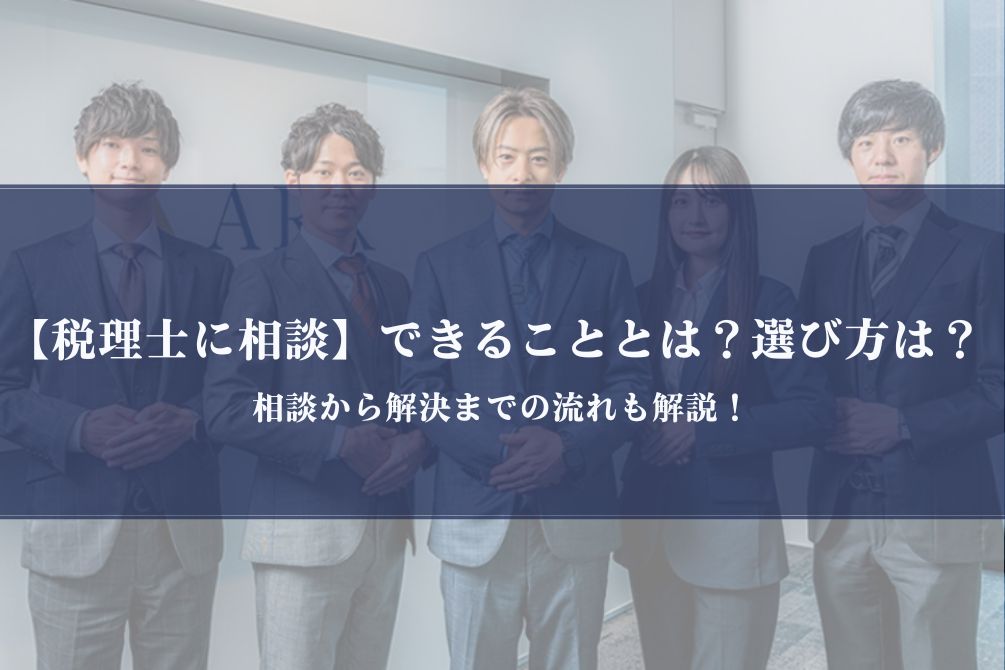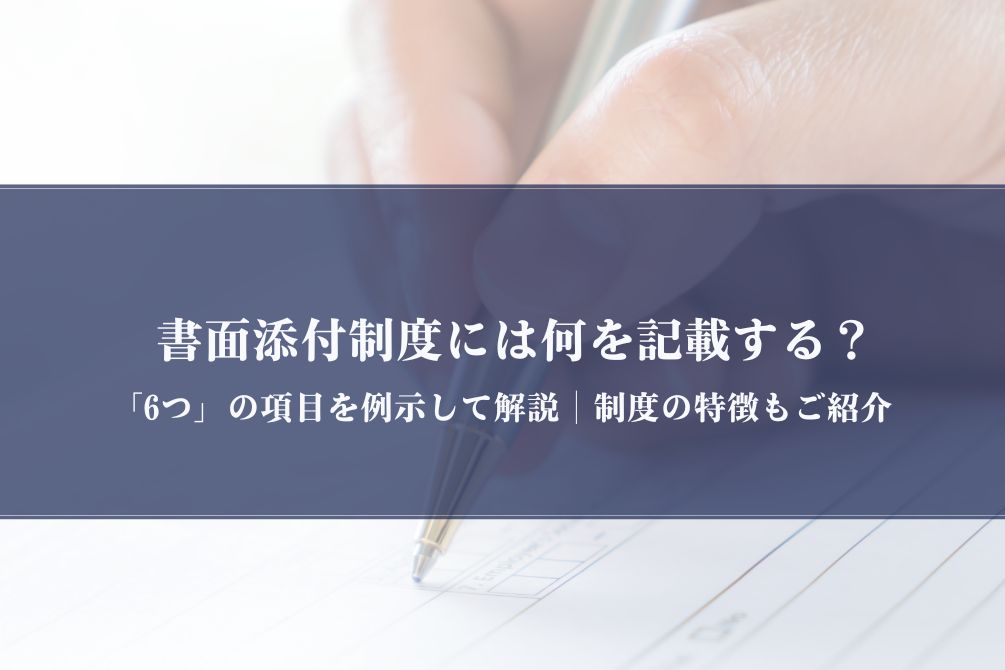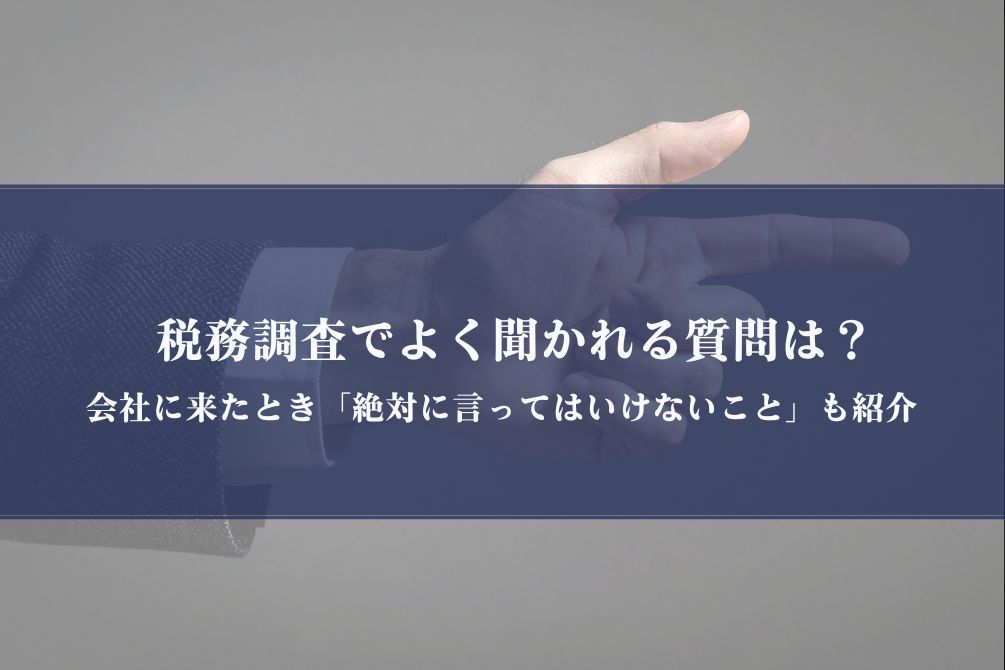【節税対策に福利厚生】確認したい10の制度│利用時の注意点もご紹介

節税を意識する経営者にとって「福利厚生」は見逃せない対策のひとつです。
適切に制度を導入すれば、法人税や社会保険料の負担を抑えながら、従業員へ利益を還元しモチベーションアップを図ることも可能です。
本記事では、節税に役立つ代表的な福利厚生制度10選と、利用時に注意したいポイントを分かりやすくご紹介します。
目次
節税と福利厚生は両立可能か?
- 節税:会社の利益を守るための税務上の対策
- 福利厚生:従業員の満足度や働きやすさを高めるための制度
このように節税と福利厚生は一見すると別々の取り組みに思えますが、実は両立させることが可能です。
福利厚生にかかる費用は「従業員のために公平に提供されるもの」と認められれば、会社の経費として計上でき、法人税の軽減につながります。
例えば社宅や食事補助、健康診断などは福利厚生費として認められ、節税効果も期待できる代表的な制度です。
福利厚生は充実させることで社員の満足度、定着率向上にもつながり、採用や人材確保の面でもメリットを期待できます。
つまり福利厚生は、単なるコストではなく、節税と人材戦略を同時に実現できる、経営上の有効な手段といえるのです。

橋場先生
自社に合った仕組みを選び、正しく運用するには専門家のサポートが欠かせません。
ARK税理士法人 では、節税と福利厚生の両立を目指す経営者の方へ、最新制度を踏まえた最適なプランをご提案しています。
節税に役立つ福利厚生制度3選
福利厚生の中には、会社の経費として計上でき、節税効果を得ながら従業員に利益を還元できる制度があります。
まずは特に実務で利用しやすい代表例を3つご紹介します。
- 決算賞与│利益を社員に還元しつつ経費計上
- 社宅制度│給与アップより効率的に手取り増
- 従業員向け法人保険│万が一の備えと節税効果
決算賞与│利益を社員に還元しつつ経費計上
決算賞与とは、決算期に利益が出た際に臨時で支給するボーナスのことです。
通常の賞与と違い、支給するかどうかを会社が自由に決められ、金額や対象者も柔軟に設定可能です。
支給額は給与と同様に経費として処理できるため、法人税の軽減につながります。
ただし「決算期末までに金額を確定・従業員に通知」「翌月末までに支給」といった期限を守る必要があります。
これを満たせば節税効果と従業員への還元を同時に実現できます。
社宅制度│給与アップより効率的に手取り増
社宅制度は、会社が賃貸契約を結び、従業員に社宅として提供する仕組みです。
給与として昇給した場合に比べ、社会保険料や所得税の増加を抑えながら従業員の手取りを実質的に増やせる点が大きな特徴です。
例えば家賃10万円のうち従業員から5万円を受け取ると、差額の5万円が経費計上可能となります。
会社側は節税しつつ従業員満足度を高められる一方で、豪華すぎる住居や負担が少なすぎる場合は課税対象となる可能性がありますので、ルール整備と適正な運用が欠かせません。
▶関連コラム:社宅制度は実は節税対策?従業員と経営者それぞれのメリット解説
従業員向け法人保険│万が一の備えと節税効果
従業員向けの法人保険は、会社が従業員の生命保険や医療保険に加入し、保険料を負担する制度です。
掛け金を会社の経費として処理できるため節税効果があり、同時に従業員の安心感や福利厚生の充実につながります。
対象となるのは生命保険・医療保険・養老保険などで、契約内容によって全額または一部が経費扱いとなります。
ただし適用は特定の従業員だけでなく全社員を対象にする必要があり、保険料という固定コストも伴うため、会社の資金計画に合わせて慎重に導入することが大切です。
▶関連コラム:【事例つき】節税vs納税(投資) 本当にお得なのはどっち!?
福利厚生で節税効果を期待できるその他7つの制度
節税につながる福利厚生は、決算賞与や社宅だけではありません。
以下のような日常的に導入しやすい制度も、適切に運用すれば経費計上や非課税扱いが可能になります。
- 食事補助│ 社員食堂や食券などを一定額まで非課税で提供できる
- 住宅手当│ 家賃補助を通じて従業員の生活を支援し経費処理が可能
- 通勤手当│ 公共交通機関利用なら月15万円まで非課税で支給できる
- 健康診断│ 法定健診に加え人間ドック費用も経費として認められる
- 研修、資格取得支援│ 業務に必要なスキルアップ費用は経費計上が可能
- 外部サービス│ 福利厚生代行サービスを活用すれば幅広い支援が利用できる
- 慶弔見舞金│ 結婚祝いや弔慰金などは社内規程に沿えば福利厚生費処理が認められる

橋場先生
自社に合った制度を選び、確実に節税効果を得たい方は、税務と福利厚生に精通した ARK税理士法人 にご相談ください。
経営規模や業種に応じて最適なプランを提案し、実務まで丁寧にサポートいたします。
節税目的での福利厚生についての注意点
福利厚生は節税に効果的ですが、導入の仕方を誤ると経費として認められないリスクがあります。特に以下の点には注意が必要です。
- 公平性の確保│全従業員を対象としなければ給与扱いとなる恐れがある
- 節税目的の強調はNG│税務調査で否認されるリスクがある
- 非課税枠・限度額の遵守│交通費や食事補助などには上限が定められている
- 社内規程の整備│支給条件や手続き方法を明文化しておく必要がある
これらを踏まえ、節税効果と社員満足度を両立させる形で運用することが大切です。
まとめ
福利厚生は、会社にとっては節税効果を得ながら従業員に利益を還元できる有効な仕組みです。
決算賞与や社宅、法人保険といった制度に加え、食事補助や健康診断など日常的な取り組みでも効果を発揮します。
大切なことは「公平性」「非課税枠の遵守」「社内規程の整備」といったルールを徹底し、節税と従業員満足度を両立させることです。
「どの制度を導入すればいいのか分からない」「節税効果を最大化したい」という方は、税務と福利厚生に精通した ARK税理士法人 にご相談ください。
最新の制度活用から実務まで丁寧にサポートし、御社に最適なプランをご提案いたします。
Contact
We will support you like a butler.