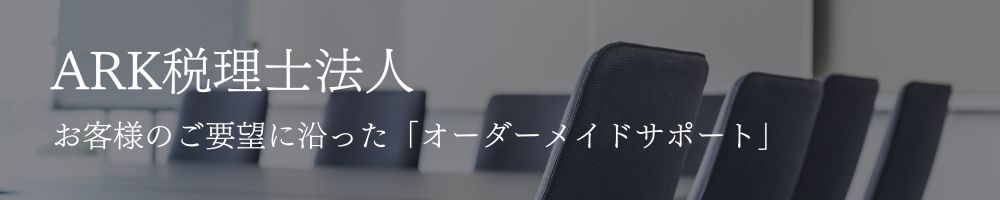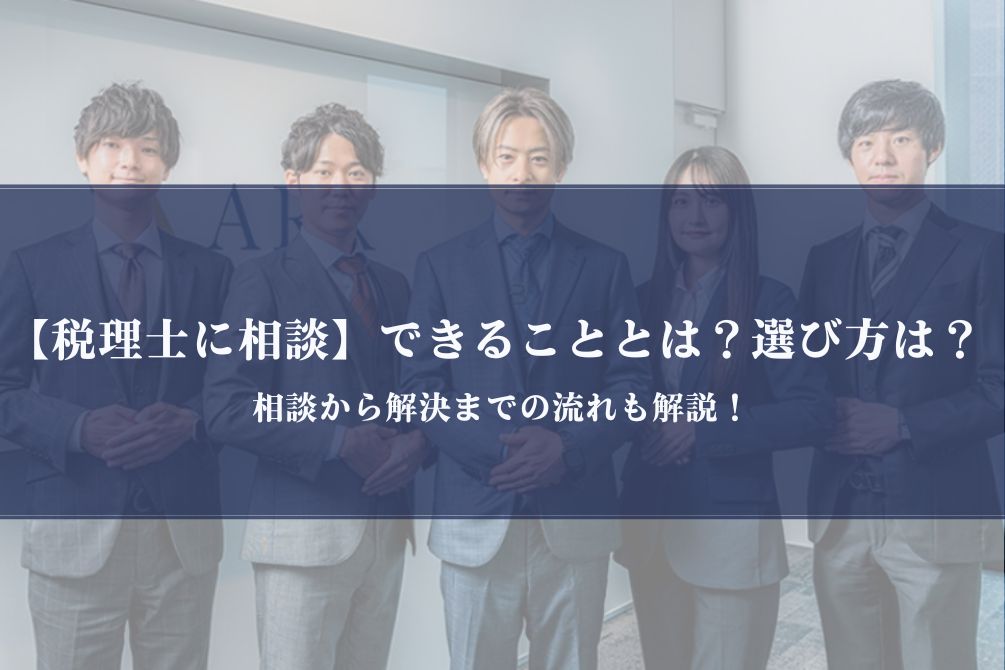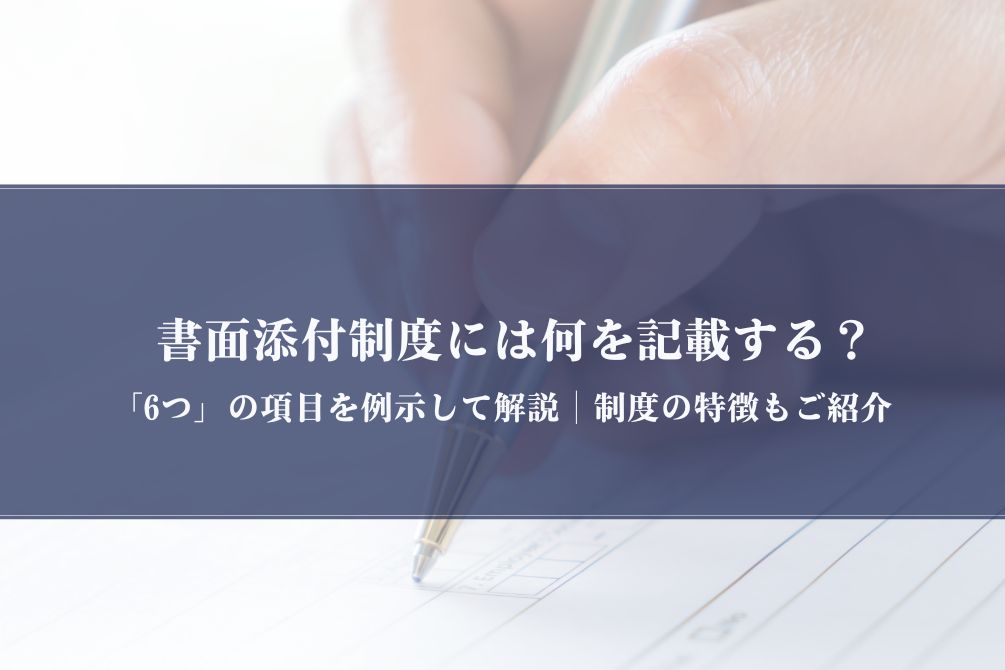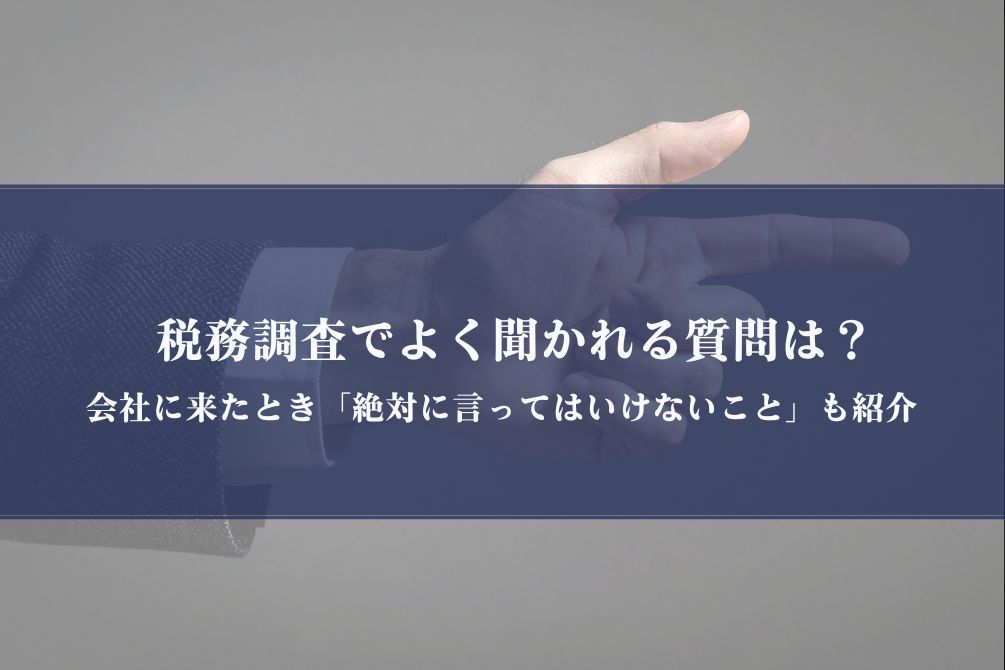【脱税はなぜバレる!?】たこ焼き売店が1億3,000万円の巨額脱税!バレる仕組みを実例解説
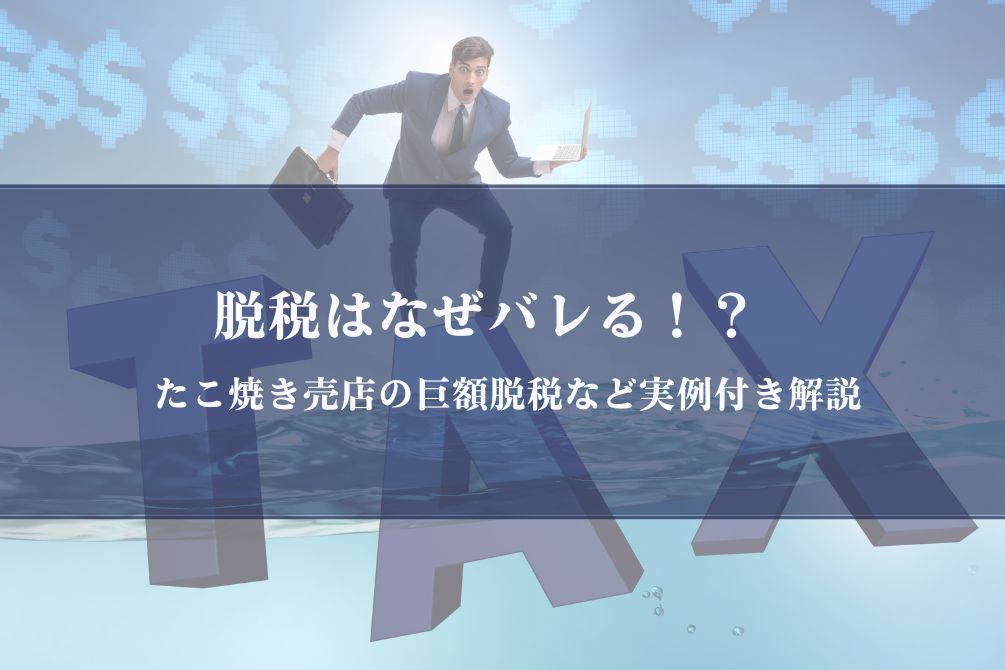
「脱税って本当にバレるの?」「現金商売なら見つからないのでは?」
このように思う方は多いかもしれません。
しかし実際には、脱税は様々なルートから発覚し、また重いペナルティが科される可能性があります。
本記事では、「脱税はなぜバレるのか?」という疑問に答えるべく、税務調査や査察調査(いわゆるマルサ)の違い、バレる主な理由、実際にあった脱税の事例を紹介します。
「自分が脱税しているのでは」と不安になる方に向けて、不安を解消するためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも「脱税」とは?
「脱税」とは、税金を意図的に免れようとする行為を指します。
たとえば、支払う税金を少なくするために、売上を少なく申告したり架空の経費を計上して所得を減らす、といった手口が代表的です。
これは、税法に違反する犯罪行為であり、重いペナルティが科されることもあります。
一方で、単なる計算ミスや知識不足による申告漏れなど、悪意のない間違いは「申告誤り」として扱われます。
これらには追徴課税や加算税が課される場合もありますが、「脱税」として刑事事件化されることは通常ありません。
つまり、「脱税」とされるかどうかは、「意図的かどうか」が大きな分かれ目です。
税務署や国税局は、その意図や証拠の有無を元に、通常の税務調査か、あるいは「マルサ」による査察調査を行うかを判断しています。
▶関連コラム:【明日 税務調査が来たら…】税理士が教える税務調査が来た時やること・流れを徹底解説!
脱税がバレる理由とは?
では、脱税がバレるのはどうしてなのでしょうか。
主には以下4つの原因で脱税がバレることとなります。
【脱税がバレる、主な4つの原因】
- 第三者からの「密告・タレコミ」
- 明らかに不自然な収支バランス
- 登記やSNSなどから生活実態が判明
- 関連者の調査から芋づる式に発覚
第三者からの「密告・タレコミ」
脱税が発覚する最大のきっかけの一つが、内部関係者や取引先、近隣住民などからの通報です。
国税庁は「情報提供窓口」を設けており、匿名での通報も受け付けています。
たとえば、元従業員が「過去に売上をごまかしていた」と証言すれば、税務署が調査に乗り出す可能性があります。
金銭トラブルや人間関係のもつれが原因となり、思わぬところから脱税が露見するケースもあるのです。
明らかに不自然な収支バランス
帳簿上の売上が極端に少ない一方で、高級車に乗っていたり豪邸に住んでいたりするなど、生活水準と申告内容が一致しない場合も疑われやすくなります。
税務署は、過去の平均値や業種ごとの利益率などのデータをもとに、不自然な数字をチェックしています。
いわゆる「売上除外」や「利益の不当な圧縮」のような典型的手法は、統計的に見抜かれやすく、調査対象に選ばれる可能性が高まります。
登記やSNSなどから生活実態が判明
脱税は「リアルの生活」からバレることもあります。
たとえば、家族や本人名義で複数の不動産を所有していたり、SNSで海外旅行や高級品の購入を頻繁に投稿している場合など、公的情報やネット上の活動が裏付け資料として使われることもあるのです。
税務調査官は、登記簿・法人登記・車両登録情報・インスタグラムなど、あらゆる情報源から生活実態を把握しています。
見られていないと思っていても、意外なところから脱税の痕跡が浮かび上がります。
▶関連コラム:【ひき肉です!】人気YouTuberの税金を勝手に予想!インフルエンサーの税金対策も解説
関連者の調査から芋づる式に発覚
税務調査や査察調査は、1つの調査が別の人物の脱税につながることも珍しくありません。
たとえば、A社の調査中にB社への不正な送金や架空取引が判明し、B社も調査対象となるという流れです。
脱税は単独で成立しないことも多く、取引先や関係会社、親族なども巻き込まれる可能性があります。
「隠していたはず」が、別の人の調査から発覚するという“芋づる式”のリスクがあることを理解しておくべきです。

橋場先生
「知らなかった」では済まされないのが税金の世界。
脱税リスクを回避し、安心して本業に集中するためには、税の専門家のサポートが不可欠です。
そんなとき頼れるのが、税務から経営、創業支援まで手掛けるARK税理士法人です。
【実例】たこ焼き屋の1億3,000万円脱税事件
実際にあった「たこ焼き脱税事件」は、脱税がどのように発覚し、どんな罰則が科されるのかを示す代表例です。
(参考)産経新聞 大阪城前たこ焼き店の巨額脱税 インバウンドで大にぎわいも「納税知らなかった」
大阪城公園内で営業していたたこ焼き店の脱税のケースでは、次のような経緯がありました。
【たこ焼き屋の1億3,000万円脱税事件の経緯】
- 約40年間にわたり無申告で営業を継続
- 年商2億円を超えていたにもかかわらず、申告ゼロ
- 税務当局が査察(マルサ)により強制調査を実施
- 所得税法違反で摘発され、懲役1年(執行猶予3年)と罰金2,600万円の判決
「納税しなければならないという意識がなかった」とのコメントが出されていますが、たとえ本人に悪意がなくても規模や状況によっては“脱税”と判断され、刑事罰にまで発展するリスクがあることを示す事例です。
脱税を過度に怖がらないために
脱税の実例を見ると「税務署が怖い…」と感じるかもしれません。
しかし、正しく申告・納税をしていれば、必要以上に恐れる必要はありません。
税務について不安を感じる方に向けて、誤解されやすい「税務調査」と「査察調査(マルサ)」の違いや、日常的に心がけるべきポイントを紹介します。
税務調査と査察調査(マルサ)の違い
税務調査と査察調査には、調査の目的と手続きに大きな違いがあります。
【税務調査と査察調査の違い】
- 税務調査:通常の確認業務。納税額の妥当性を確かめる任意の調査。事前通知あり。
- 査察調査:明らかな脱税の疑いがある場合に行われる強制調査。事前通知なし・令状あり。
査察調査は刑事事件として扱われ、逮捕や起訴に至ることもあります。
一方で、一般的な企業や個人事業主が受けるのは、ほとんどが税務調査です。
通常は査察調査を受けることはない
査察調査(マルサ)に入られるのは、意図的で悪質な脱税が疑われる場合に限られます。
たとえば、売上除外や架空経費などの証拠が明確にある、長期間にわたって無申告を続けている、といった例が該当します。
通常の経理処理のなかで生じた申告ミスや軽微な修正で、いきなり査察が来ることはありません。
つまり、日ごろから誠実に申告・納税していれば、過度に怯える必要はないということです。
日頃から経理・帳簿を適切に整備する
「怖がらなくていい」とはいえ、経理を適当にしてよいわけではありません。
正確な帳簿や領収書の保存、売上や経費の正しい仕訳は、調査が入った際に自分を守る最大の防御策です。
【適切な税務処理のために心がけることの例】
- 領収書・請求書を適切に保存
- 現金の出入りを明確に記録
- 会計ソフトで日々の仕訳を正確に行う
- 税理士など専門家に早めに相談する
これらを継続していれば、仮に税務調査があっても落ち着いて対応でき、重い指摘を受けることも少なくなります。
▶関連コラム:税務調査が来なくなる!?書面添付制度について税理士が徹底解説!

橋場先生
脱税リスクを回避するために必要なのは、「正しい知識」と「日々の適切な経理処理」です。
とはいえ、不安や迷いがあるなら、税務のプロに早めに相談すると安心です。
税務から経営まで幅広く相談できる税理士をお探しなら、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
まとめ
脱税は「バレなければ問題ない」と考えがちですが、実際にはタレコミや登記、収支の不一致など、さまざまな情報から発覚しています。
悪質と判断されれば査察(マルサ)が入り、刑事罰に至るケースも少なくありません。
とはいえ、日頃から帳簿や領収書を整備し、正しく申告していれば、過度に怖がる必要はありません。
また、不安な点や判断に迷うことがあれば、早めに税理士に相談することが最善のリスク回避となります。
税務のトラブルを未然に防ぎたい方は、税務から経営、創業などへの支援も実施するARK税理士法人へお気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.