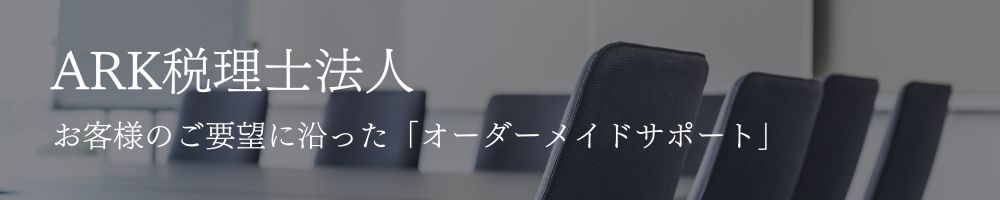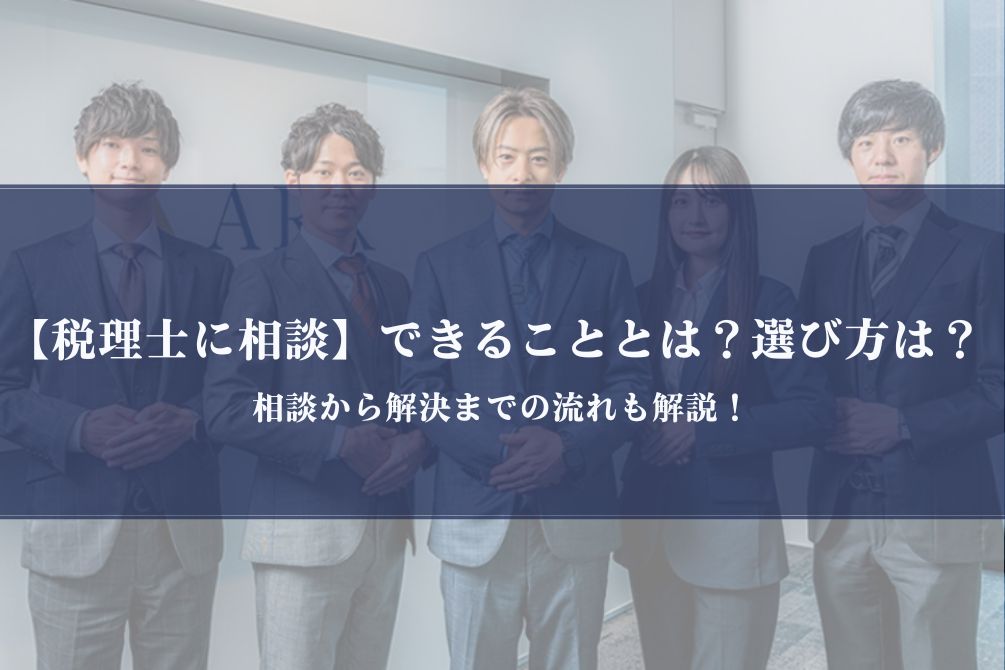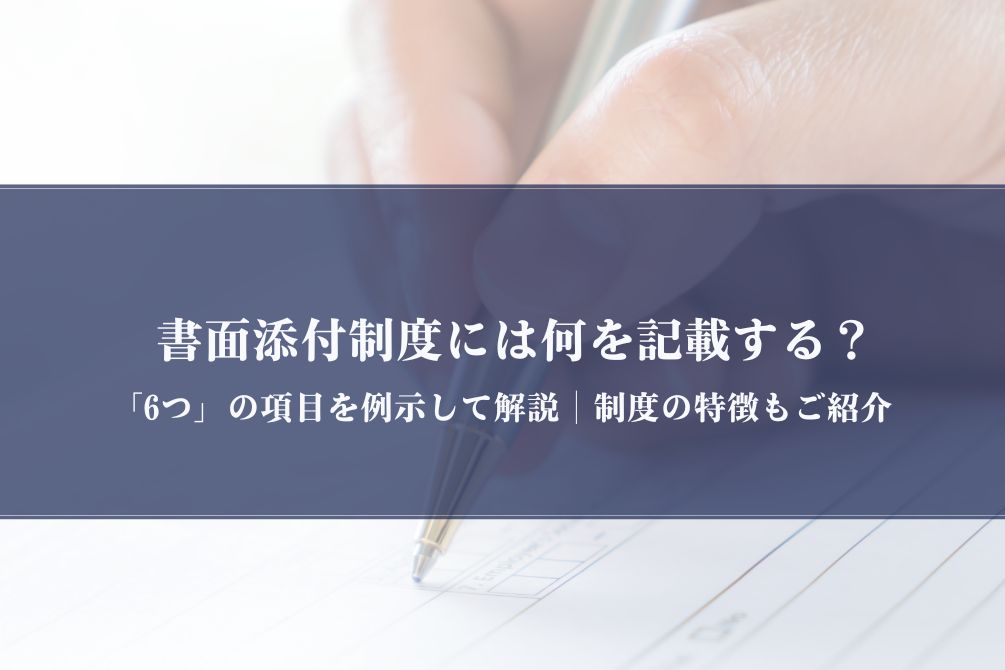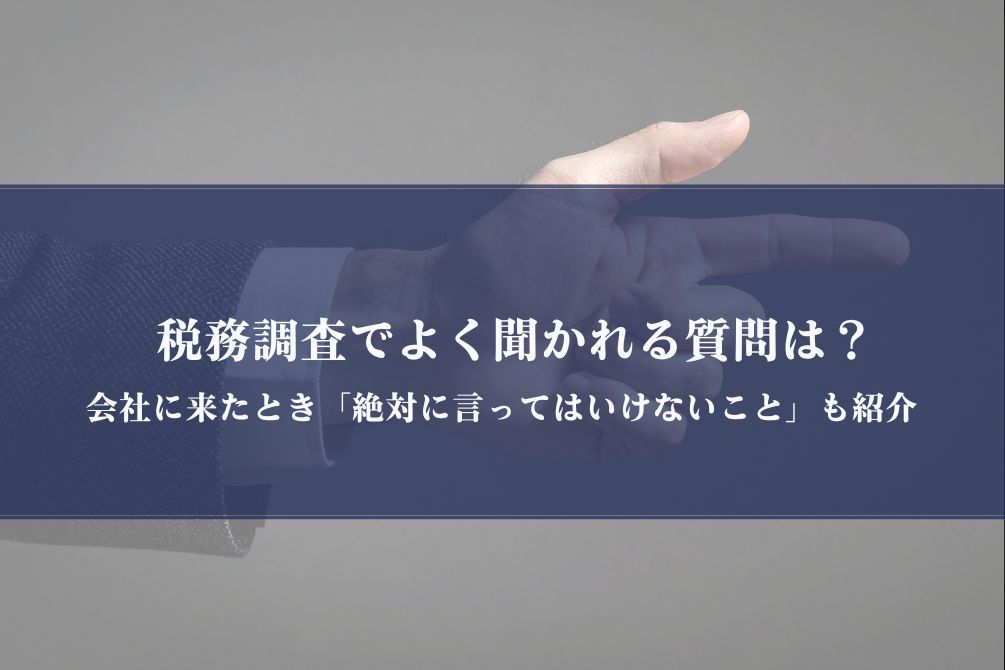【例題つき】医療費控除の計算方法は?制度の仕組みといくら戻るか徹底解説!
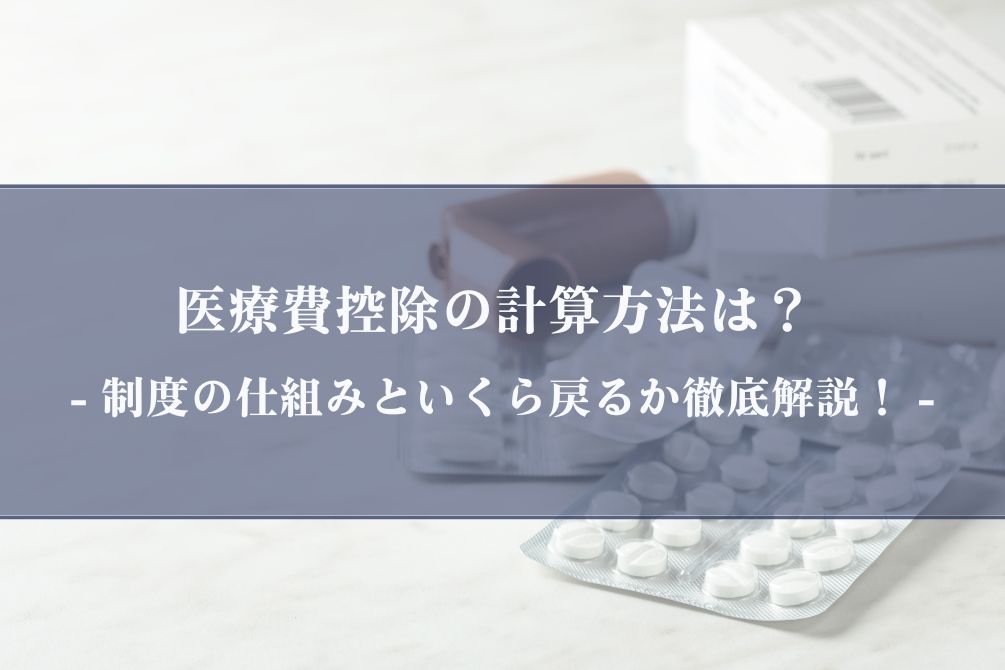
『医療費控除』という単語はよく聞くものの、どのような制度なのか、またどの程度税金がお得になるのか、といった詳細はご存知ないのではないでしょうか。
医療費控除を利用することで、一年間に支払った医療費が高額である場合、手続きをすることで所得税が軽減され、税金の還付を受けられる可能性があります。
本記事では、医療費控除とはどういった制度か、制度の仕組みや計算方法を解説した上で、実際にどのくらい戻るのか、金額をシミュレーションします。
どういった支出が対象となり、また対象とならないのか、といった気になるポイントも解説しますので、節税を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
医療費控除とは?制度の仕組みと計算方法を紹介
はじめに、医療費控除とはどういった制度なのか、仕組みや計算方法について解説します。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が基準となる金額を超える場合に、手続きを取ることで基準額を超えた分の医療費が所得から控除される仕組みです。
具体的には、自分や家族のために支払った医療費が年間10万円を超えた場合に、10万円を超えた部分の金額が所得から差し引かれることとなります。
その結果、課税対象となる所得を減らすことができ、支払う税金を安く抑えることが可能となります。
実際に計算するときは、以下の式で計算します。
1~12月に支払った医療費 – 10万円または所得税額の5% (低い方)= 医療費控除額
より分かりやすく解説するために、具体的な金額を設定してシミュレーションしましょう。
医療費控除でどのくらい戻る?金額シミュレーション
今回、医療費控除の金額シミュレーションで使用する条件は以下のとおりです。
- 1年間に支払った医療費:40万円
- 税率:30%(所得税率+住民税率=約30%と仮定)
この場合に医療費控除で受けられる節税額は、以下のとおりです。
(1)医療費控除額を算定する
40万円(医療費) – 10万円(医療費から差し引く金額) = 30万円(医療費控除額)
(2)医療費控除による節税金額を算定する
30万円(医療費控除額) ✕ 30%(税額) = 9万円(医療費控除による節税額)
このように医療費控除を利用することで、9万円もの税金を節税できることが分かります。

橋場先生
医療費控除は、ご自身で申請しなければ受け取れない節税策です。
本制度以外にも、自分から申請する必要のある制度は多くありますので、「税金が高い」と感じている方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
医療費控除を利用する上での注意点
活用することで所得税、住民税を節約できる医療費控除ですが、利用を検討する場合に注意するべき点もありますので紹介します。
対象となるもの、ならないものがある
本制度は、控除の対象となるもの、ならないものがあります。
仕分けが誤っていれば、後で指摘を受けて追加の税金を支払ったり、逆に節税の効果が薄くなる恐れもありますので注意が必要です。
制度の対象となるもの、ならないものの例を記載しますので、仕分ける際の参考にしてください。
【医療費控除の対象となるものの例】
- 診療費、治療費
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 診療を受けるための通院費
- 入院のための部屋代や食事代
- 医療用器具の購入費 など
【医療費控除の対象とならないものの例】
- 健康診断の費用
- 医師に対する謝礼
- ビタミン剤など、病気の予防や健康増進目的の医薬品購入費
- 通院に利用するタクシー代
- リラクゼーション目的のマッサージ代
- 美容のための整形代 など
給付金や保険金を差し引く必要がある
本制度が対象とする控除金額は、自分で負担した医療費に限られます。
このため、公的機関からの給付金や保険会社から支払われた給付金などを、医療費から差し引いて計算しなければいけません。
セルフメディケーション税制は選択適用になる
医療費控除と似た制度に、セルフメディケーション税制があります。
セルフメディケーション税制は、健康維持や病気予防を目的として医薬品を購入した場合、12,000円を超える部分について所得から控除を受けられる制度です。
(参考)国税庁 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となりますので、どちらか一方を選んで所得控除を受けることとなります。
確定申告が必要になる
医療費控除を利用する場合、職場などで受ける年末調整とは別に、税務署に対して次のような流れで確定申告をする必要があります。
- 医療費控除の対象となる領収書などを集め、医療費を計算する
- 確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
- 本人確認書類など、必要書類とともに税務署に提出する
慣れれば簡単な手続きですが、初めて確定申告する場合は手間取る可能性があります。
簡単にスマートフォンで申告できるアプリもありますので、医療費控除のみ申請する場合などは利用してみましょう。

橋場先生
医療費控除やセルフメディケーション税制など、納税額を抑える制度は実は多くあります。
意識的に利用しなければ、支払わなくてもよい税金を支払うこととなりますので、一度税金の専門家に相談することをおすすめします。
相談先が分からない場合は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
まとめ
該当する年の1月1日から12月31日までの期間中、医療費が一定の金額を超えた場合に利用できる、医療費控除について解説しました。
シミュレーションでお伝えしたとおり、本制度を利用することで税金額が安くなる可能性がありますので、「今年はたくさん病院に通った」このように思う方は、医療費控除の利用を検討しましょう。
領収書など、準備するべき書類もありますので、利用を検討する方は早めに用意することをおすすめします。
不明な点がある方はARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.