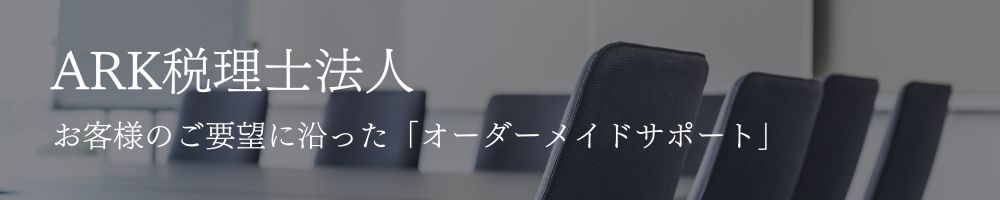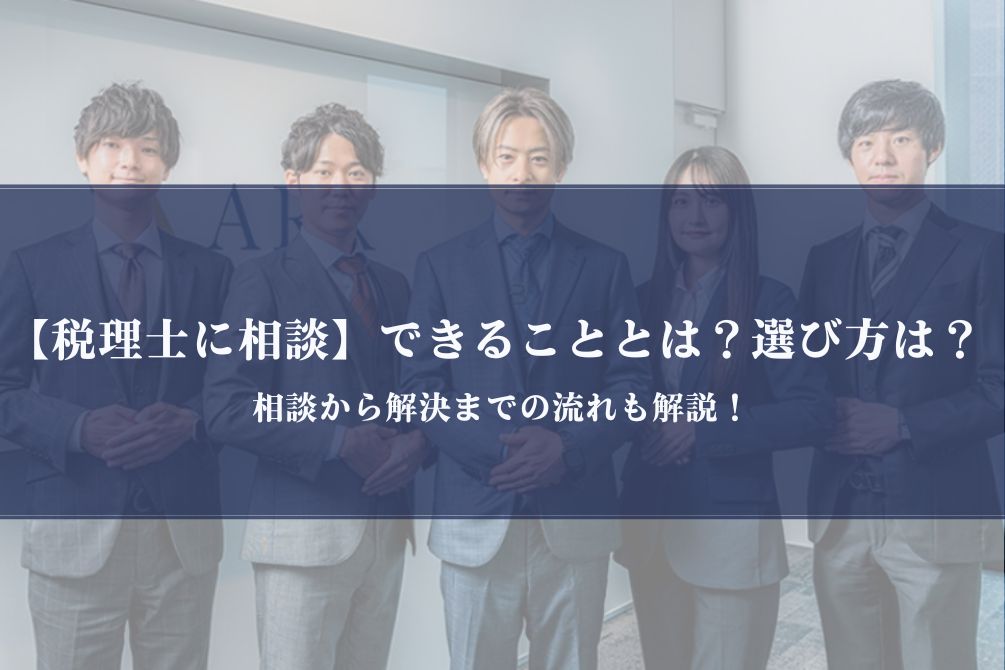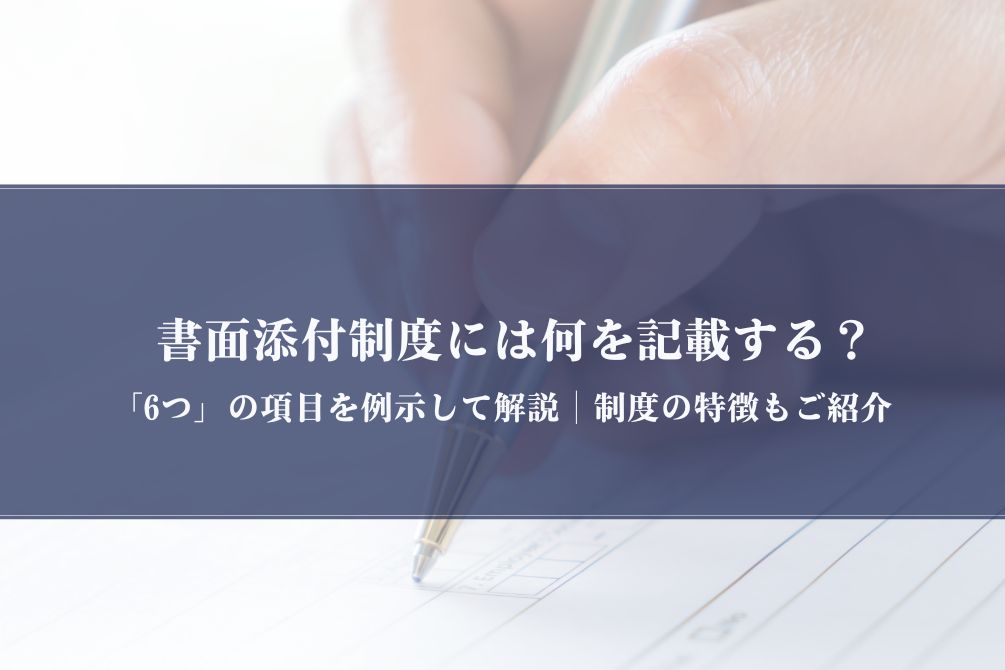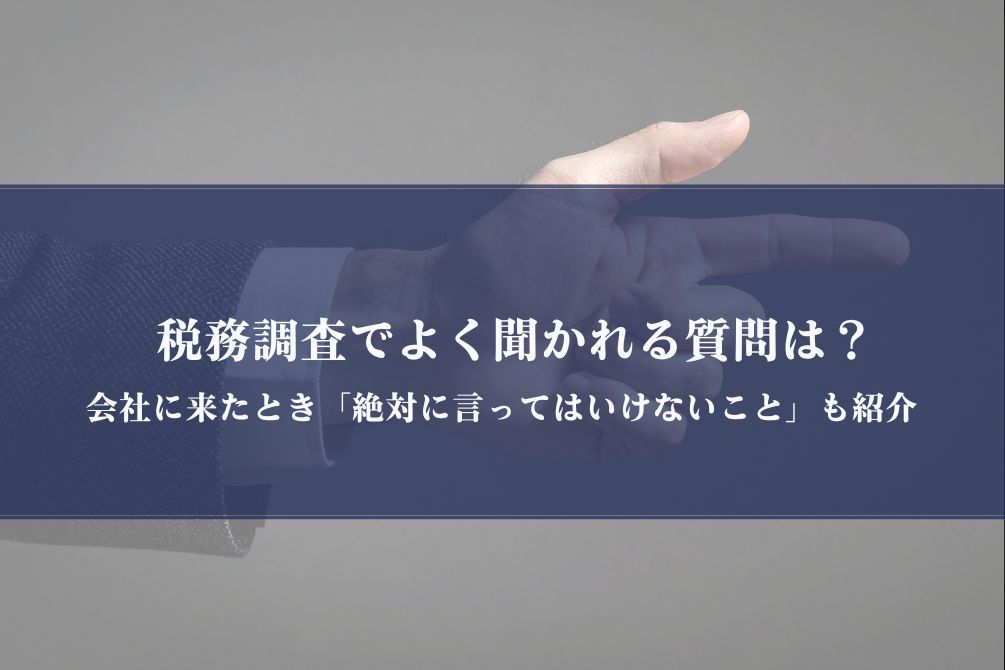結婚したら節税!利用できる「制度早見表」得する働き方と制度の組み合わせも解説
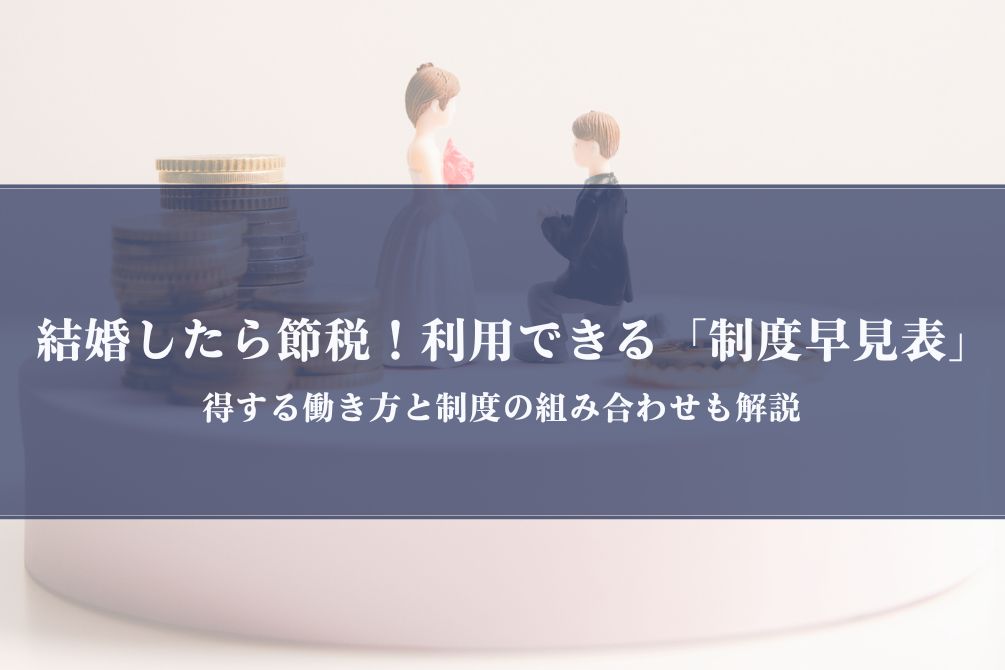
「結婚して夫婦になると、税金が安くなる」
そんな話を耳にしたことはありませんか?
実は結婚すると、「配偶者控除」や「社会保険の扶養」といった制度を活用して節税でき、実質的な手取りを増やすことが可能です。
制度を正しく理解することは、世帯全体の手取りを増やすことにもつながります。
結婚して、生活資金のほか教育資金や老後資金に対して不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
【早見表】結婚で使える主な節税(控除・非課税)制度
はじめに、結婚を機に利用できる代表的な制度を一覧で整理します。
ご家庭の状況に応じて、利用できる制度があるか確認しましょう。
【結婚したら利用できる節税制度、早見表】
● 配偶者控除、配偶者特別控除
配偶者の所得が一定以下の場合に、所得税と住民税が軽減される制度(最大38万円+33万円の控除)。
● 社会保険の扶養(106万円、130万円)
収入が一定以下の配偶者を扶養に入れると、健康保険料と年金保険料の負担が免除される仕組み。
● 住宅ローン控除(ペアローン)
夫婦それぞれが借入を行い、住宅ローン年末残高の0.7%を13年間所得税から控除できる制度。
● 贈与の非課税枠(結婚子育て資金、住宅取得資金)
両親や祖父母からの資金援助を受けても、条件を満たせば一定金額は非課税になる制度。
● 自営業の節税(青色事業専従者給与)
家族に支払う給与を経費として計上でき、所得税を軽減できる制度。
それぞれの制度について、さらに詳しく解説していきます。
配偶者控除、配偶者特別控除
配偶者の年間の所得が48万円(給与収入で103万円)以下であれば、配偶者控除が適用されます。
また、103万円を超えた場合でも、201万円未満までは配偶者特別控除を段階的に適用可能です。
年末調整や確定申告の際に申告することで一定の金額の控除(最大38万円+33万円の控除)を受けることができ、所得税と住民税が軽減されます。
社会保険の扶養(106万円、130万円)
収入が一定以下の場合、配偶者を健康保険と年金の扶養に入れることができます。
目安は勤務先の条件によって異なりますが、
- 大企業勤務など厚生年金加入者:106万円
- 中小企業、パート勤務など:130万円
扶養に入ると保険料の自己負担がなくなりますので、月数万円単位で家計にゆとりが生まれます。
なお、本制度は扶養の対象となる金額の上限が引き上げられる議論が行われています。
今後制度が変わる可能性がありますので、動向に注視することをおすすめします。
住宅ローン控除(ペアローン)
共働きの方がマイホームを購入する際に節税効果を最大化できる制度が「ペアローン」です。
夫婦それぞれが住宅ローンを組むことで、それぞれに住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用されます。
- 年末残高の0.7%を、最長13年間所得税から控除
- 夫婦それぞれが控除を受けられる(共働きで効果倍増)
なお、ペアローンを利用すると多額の資金を借り入れられますが、ボーナスの減額など収支の変化への対応力が弱まりますので、ライフプランと資金計画を含めて計画的に利用することがポイントです。
贈与の非課税枠(結婚子育て資金、住宅取得資金)
親や祖父母からの資金援助を受けるとき、一定の条件を満たせば贈与税がかからない制度があります。
結婚や住宅購入のタイミングでは、上手に活用することで大きな節税効果を得られます。
結婚、子育て資金の一括贈与:最大1,000万円まで非課税
- 親や祖父母から子や孫へ結婚、出産、育児、教育資金をまとめて贈与できる制度。
- 最大1,000万円(結婚関連は300万円)まで非課税。
- 領収書提出などの手続きが必要で、未使用分は将来的に課税される場合もある。
(引用)国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
住宅取得資金の贈与:最大500万〜1,000万円まで非課税(住宅性能による)
- 親や祖父母から、住宅の購入や新築、リフォーム資金を贈与された場合に使える制度。
- 省エネ、耐震などの高性能住宅なら、最大1,000万円まで贈与税が非課税に。
(引用)国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
計画的に利用すれば、数百万円単位の贈与を非課税で受け取れる可能性があります。
▶関連コラム:【贈与税対策】生前贈与で数百万円の節税!?直近の改正や節税シミュレーションも紹介
自営業の節税(青色事業専従者給与)
自営業者が配偶者や家族を仕事に従事させている場合、「青色事業専従者給与」を活用することで、支払う給与を経費として計上できます。
配偶者への給与の分だけ所得税や住民税を軽減できますので、自営業者は積極的に活用したい制度です。
正しく届出や記帳を行えば、効果的な家族内節税策として活用できます。

橋場先生
制度の多くは、「年末調整」や「確定申告」で届出をして初めて税金額に反映されます。
逆に、申請しなければ不要な税金を支払うことになりかねません。
ご家族の状況に応じて節税の方法を知りたい方、サポートを受けたい方は、ARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
ケース別「得する働き方×制度」の組み合わせ
このように、結婚に関連して節税を図れる制度は多くありますが、働き方によって利用するべき制度が変わる点に注意が必要です。
では、具体的にどの制度を利用するべきなのか、ケース別にお伝えします。
片働き(会社員+専業主婦/主夫)|配偶者控除と扶養をフル活用
収入のない配偶者を扶養に入れることで、所得税、住民税が軽減され、社会保険料の負担もゼロにできます。
配偶者控除や健康保険の扶養を組み合わせれば、年間10万円以上の節税も可能ですので、専業主婦(主夫)世帯では、最も効果的な基本節税パターンといえます。
共働き(年収差が小さい)|控除分散より“手取り最大化”のコツ
夫婦の収入がほぼ同じくらいなら、「どちらが払うか」を工夫するだけで手取りが変わります。
医療費や生命保険料、ふるさと納税などの控除は、税金が多くかかる方(少し年収が高い方)がまとめて申告すると効果的です。
たとえば、夫婦で同じ額の保険料を払うより、どちらかに寄せて支払う方が控除額が増えるケースもあります。
▶関連コラム:【個人事業主必見】ふるさと納税は結局お得なのか?年収シミュレーションで解説
共働き(年収差が大きい)|医療費、保険料の支払者設計で差をつける
夫婦の収入差が大きい場合は、税率の高い方(年収の高い側)に控除を集めることが節税のコツです。
医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを高所得者名義で支払うと、同じ控除額でも税率が高い分、還付、節税効果が大きくなります。
▶関連コラム:【所得税の節税は『所得控除』から】今日から節税に使える「所得控除12選」をご紹介
産休、育休、パート切替期|配偶者特別控除を取り逃さない
育休や時短勤務などで一時的に収入が減った年は、配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
年収が201万円未満であれば段階的に控除が適用されますので、勤務形態が変わるタイミングでは再計算が必須です。

橋場先生
このように結婚に関わる制度は、ご夫婦やお子さまの有無、家計の収支の状況などによって最適な節税対策は変わります。
ケースごとに試算をしなければ正しい節税はできませんので、最適な資産の配置で税金を抑えたい方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
まとめ
結婚を機に利用できる節税制度は、実は想像以上に多くあります。
とくに「配偶者控除」「社会保険の扶養」「住宅ローン控除」といった制度は、多くのご家庭に関係する重要ポイントです。
夫婦で働き方を話し合い年収見込みを整理することで手取りを増やし、将来の資産形成につなげましょう。
こうした税金や節税の仕組みを知ることは、家計を守る第一歩です。
制度の詳しい条件や、最もお得な組み合わせ方を知りたい方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.