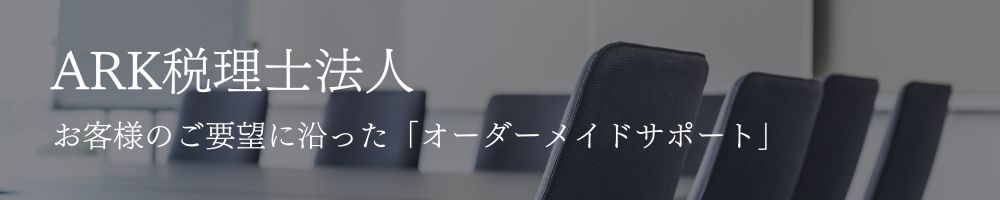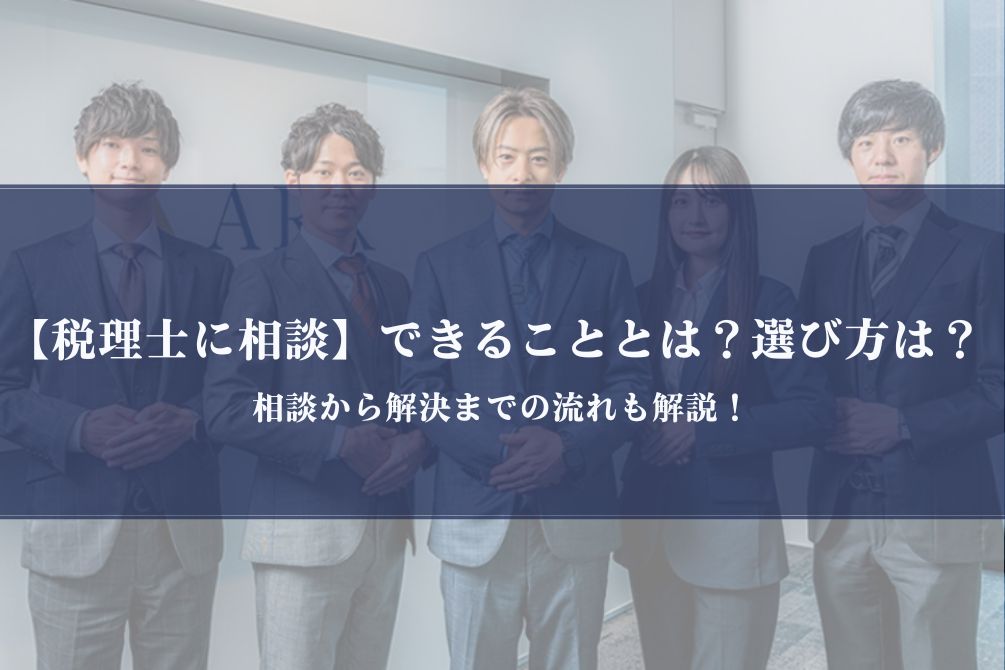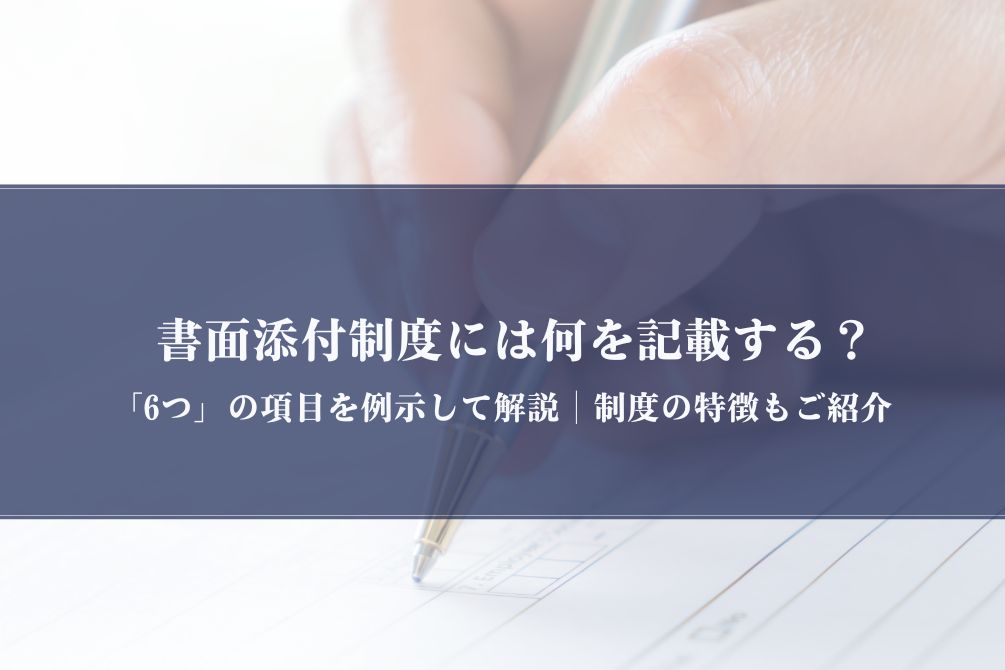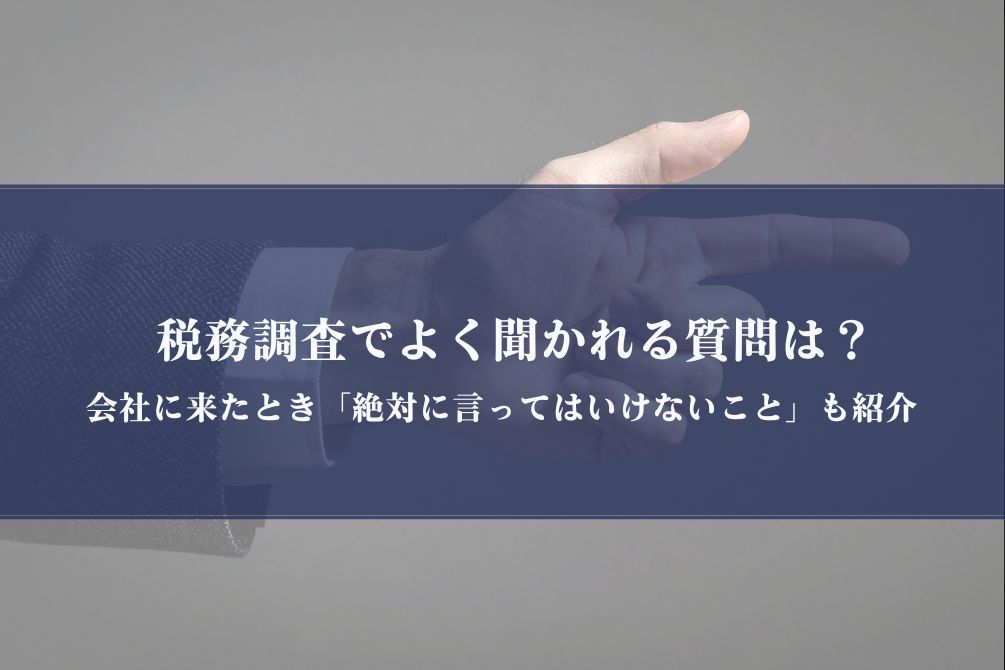電子帳簿保存法の保全要件とは?確定申告に向けて効率的に管理できる「プロの管理法」もご紹介
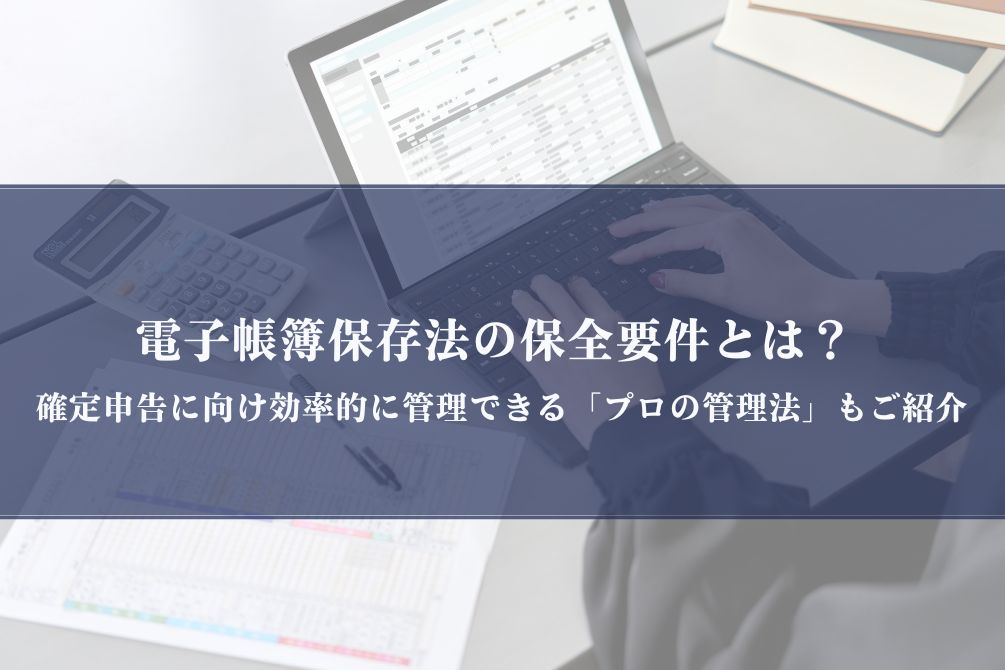
確定申告に関連して、「電子帳簿保存法(電帳法)」という言葉を聞いたことがある方も多いもの。
一方で「結局何をすればいいの?」と疑問に感じたり、実際の作業にまで至っていない方も多いのではないでしょうか。
しかし実は、請求書や領収書をメールで受け取る機会が増えている昨今、正しく保存していなければ税務調査で指摘を受けるリスクがあります。
また、制度を上手に活用すれば、業務の効率化や省スペース化などメリットがあることも事実です。
そこで本記事では、電子帳簿保存法の基礎や要件、専門家が実践している効率的なデータ管理法まで解説します。
目次
そもそも電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、帳簿や請求書などを紙ではなく電子データで保存できるよう定めた法律です。
元々確定申告に関係する書類は7年間保存する義務がありますが、デジタル化の流れで、電子データでの管理を認める制度に変わりました。
特に2024年からは、メールやクラウド経由など電子取引で受け取ったデータの保存が義務化されるなど、電子データでの保存は重要性を増しています。
▶関連コラム:【確定申告・超初級編】今さら聞けない!対象の人・準備・スケジュールを税理士が徹底解説!
電子帳簿保存法の「保存要件」とは?3つの区分を確認
このような電子帳簿保存法、実は保存方法が3つに分かれています。
制度を利用する際に必要ですので、対象や特徴を確認しましょう。
- (1)電子帳簿等保存:会計ソフトで作成した帳簿のデータ保存
- (2)スキャナ保存:紙の領収書や請求書を画像データ化し保存
- (3)電子取引データ保存:メール・クラウドなどデータ取引の保存
このうち「電子取引データ保存」は紙に印刷しても、税務上の書類としては認められない点に注意が必要です。

橋場先生
義務化されたルールを知らずに運用していると、経費が否認されるリスクもあります。
制度の対応や保存体制の見直しは、専門家への相談がおすすめです。
ARK税理士法人では、制度対応から具体的な運用方法のご提案まで一貫サポートしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
電子帳簿保存法、どこまで義務?どこまで任意?
電子帳簿保存法について誤解されやすい事柄のひとつは、「全てデータ化しなければ違法になるのでは?」ということです。
実は2025年現在義務化されているのは、メールやクラウド上による電子取引データの保存に限られます。
つまり、紙でもらった書類をスキャンして保存することは「任意」です。
ただし、電子保存への切り替えは以下のようなメリットがあります。
- 書類の保管スペースを節約できる
- 大量の書類から簡単に検索できる
- 確定申告書との紐づけがスムーズに行える
このため、業務効率の向上を目指す場合は、各種書類を電子化することをおすすめします。
電子取引データ保存の要件を詳しく解説
加えて注意が必要な点は、電子取引データを保存する場合、国税庁が定める要件を満たす必要がある点です。
具体的には、主に次の3つのポイントが該当します。
- 改ざん防止措置:タイムスタンプや履歴管理、社内規定での対応が必要
- 検索要件:日付・金額・取引先名で検索できる状態にしておく
- 保存期間:原則7年(特定条件の青色申告の法人は10年)
全てを自力で実行することは困難に思えますが、近年発売されている会計ソフトには、自動対応できる仕組みが整っているものもありますので試してみましょう。

橋場先生
間違った認識で作業を続けた場合、労力が無駄になったり、経費として認められなくなる恐れもあります。
制度の内容や実際の作業で不明な点がある方は、ARK税理士法人にお気軽にご相談ください。
プロがやっている、効率的なデータ管理法
電子帳簿保存法について作業をしていると、「もっと簡単に作業できないだろうか」このように思うこともあります。
そこで記事の終わりに、税理士や経理担当者が実際に行っている管理法についてご紹介します。
- スキャナ(ScanSnapなど)の活用で紙資料をデータ化
- 会計ソフトと連携して仕訳を自動登録
- 事務処理規程を作成し運用ルールを明確化
- クラウド保存でデータ消失リスクを防ぐ
- 電子保存の定期点検を四半期ごとに実施 など
電子データの効率的な管理は、事業者の規模や業種によって異なります。
最適な方法を模索している方は、税理士など会計処理の専門家に相談してみましょう。
まとめ
確定申告に関係する書類を電子データとして取り扱う、電子帳簿保存法について、制度の内容や実務を解説しました。
本制度は確定申告に代表される会計処理の手間を大幅に軽減できる制度ですが、紹介したとおり様々な決まりがあります。
個人で調べながら対応することも可能ですが、時間を節約するためには専門家に相談することもおすすめです。
たとえばARK税理士法人では、以下のようなご相談を承っております。
- 電子帳簿保存法対応の初期設定、運用サポート
- 事務処理規定の作成とチェック
- 経理の自動化支援 など
他の事務作業もまとめてご相談可能ですので、「何から始めればいいのか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.