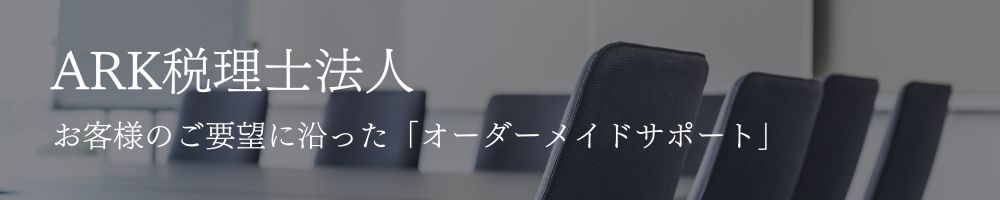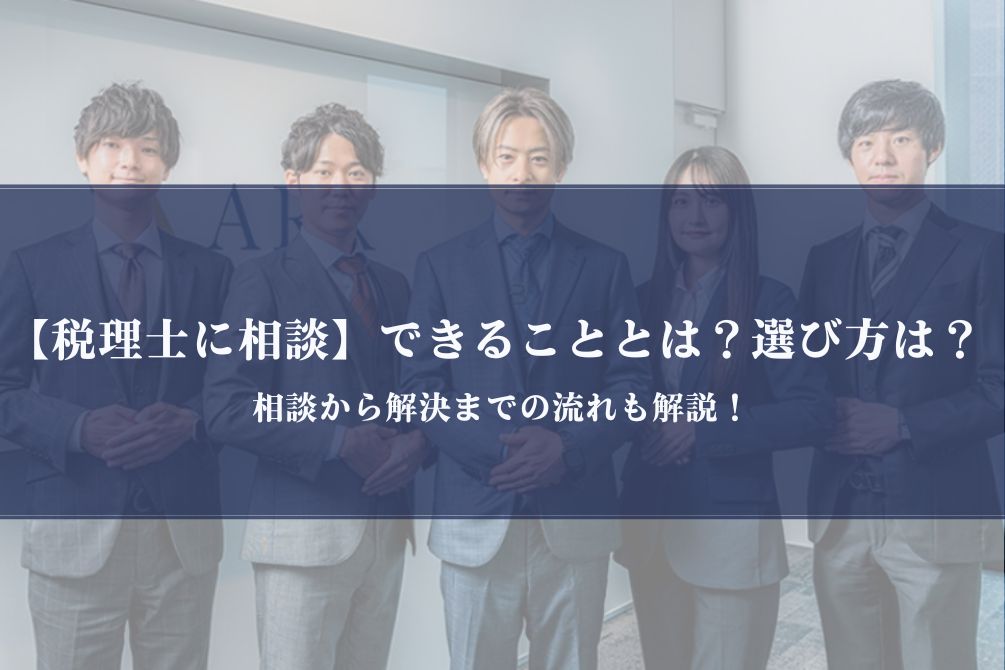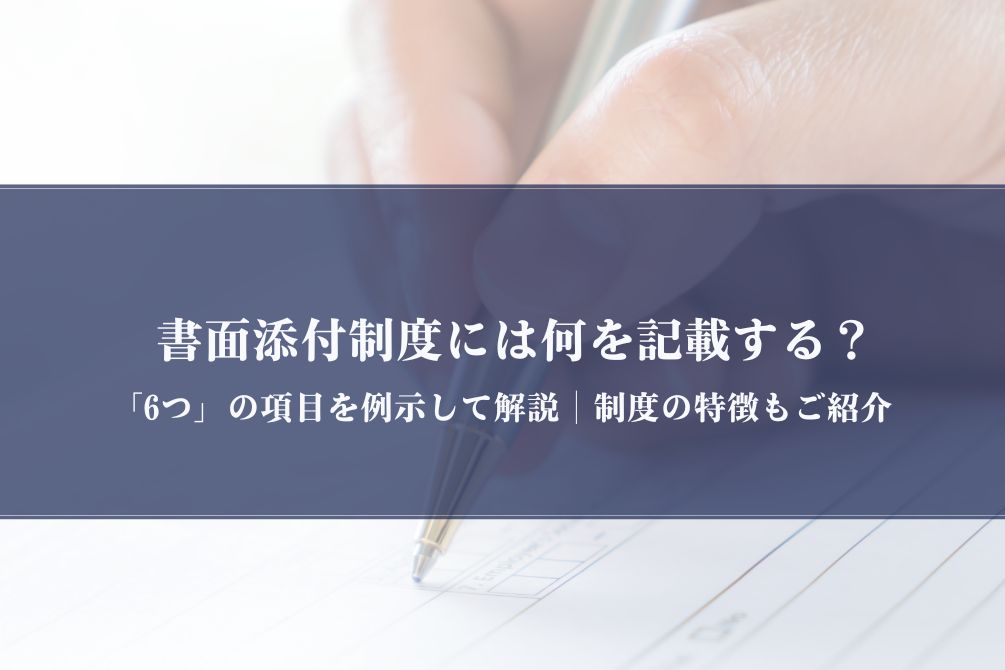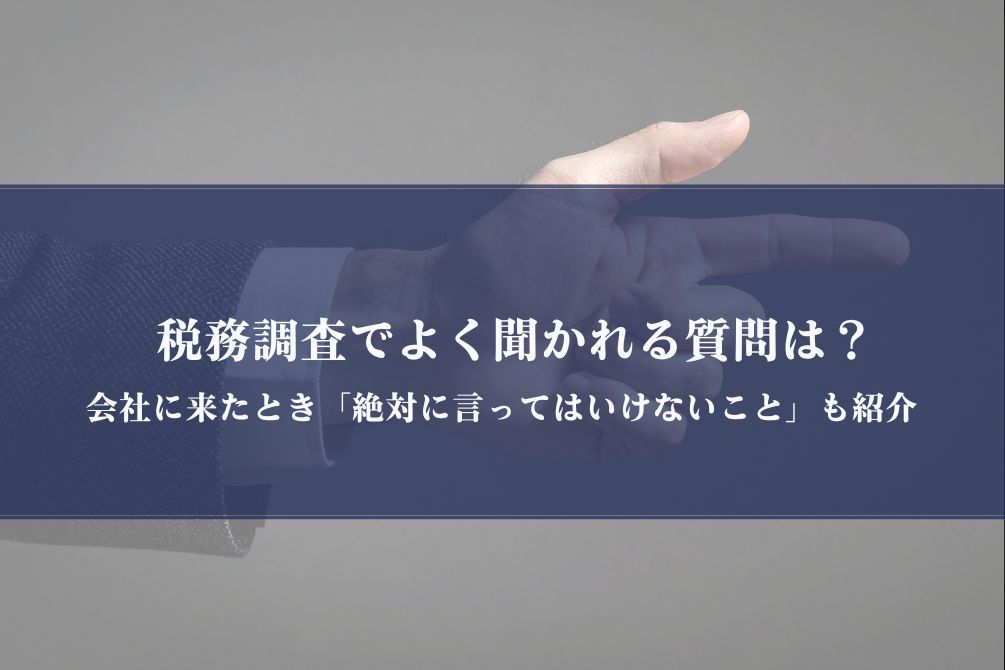個人でできる『確定申告対策』今からできる節税&事務負担を減らす準備法を解説
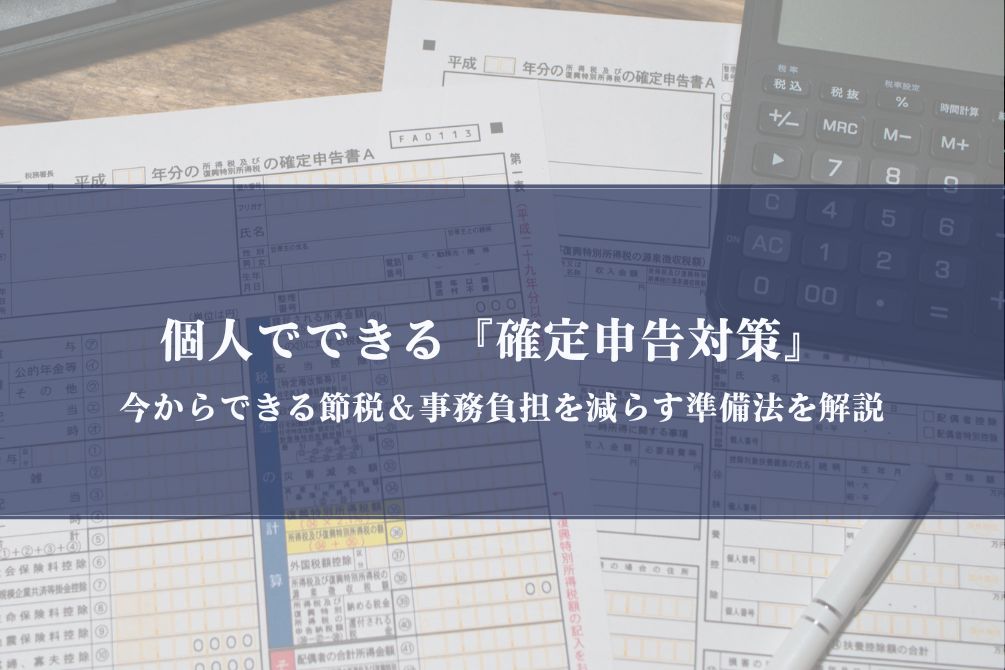
「確定申告の時期になると、慌てて書類を集めて徹夜でを作業している」
こうした方は少なくありません。
その原因は、日々の記帳など処理を後回しにすることで、確定申告の締め切り期限である3月15日がいつの間にか到来することにあります。
しかし実は、個人の確定申告は適切な対策を取れば、手間も税金も軽減することは可能です。
本記事では、個人事業主やフリーランスの方が今から実践できる確定申告対策を、節税と効率化の両面から解説します。
目次
そもそも確定申告とは?誰がする必要があるの?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に応じた税金をご自身で計算し、税務署に申告するとともに納税する手続きのことです。
誰もが申告が必要になる訳ではなく、次の基準に該当する方のみ申告の義務が生じます。
【確定申告が必要になる方の例】
- 給与所得が2,000万円を超える人
- 年金収入が400万円を超える人
- 副業などで年間20万円以上の所得がある人
- 給与を2か所以上から受け取っている人 など
会社員の方でも条件によっては申告が必要になりますので、「自分は関係ない」とは思わずに確認しましょう。
▶関連コラム:【確定申告・超初級編】今さら聞けない!対象の人・準備・スケジュールを税理士が徹底解説!

橋場先生
確定申告の対象や必要な手続きを正しく理解しておくことで、無駄な税負担や申告ミスを防ぐことができます。
「自分の場合は申告が必要なのか分からない」「税金を節約する方法を知りたい」このように思う方は、ぜひ一度ご相談ください。
今すぐできる確定申告対策【個人事業主・フリーランス向け】
「まだ年度末ではない」と油断すると、いつの間にか期限が到来してしまい、控除の申告漏れや経費の計上ミスが多発します。
ミスをなくすためには、以下3つの対策を取ることをおすすめします。
- 積立型の節税制度(小規模企業共済、倒産防止共済、iDeCo)
- 経費の計上による節税
- 会計作業を効率化するツールを導入
積立型の節税制度(小規模企業共済、倒産防止共済、iDeCo)
1つ目は、掛金の支払いが節税につながる、積立型の控除制度です。
代表的なものは、次の3つです。
- 小規模企業共済:自営業者・役員などの退職金制度。掛金は全額所得控除。
- 倒産防止共済:取引先倒産時の資金繰りを支える制度。掛金は全額経費に計上可能。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):老後資金を積み立てながら節税できる制度。
ただし、倒産防止共済は「1年以上事業を継続していること」、小規模企業共済は「会社員との兼業は不可」といった制限もありますので注意しましょう。
▶関連コラム:【個人事業主の厚生年金の代わり】小規模企業共済、4つのメリット・2つのデメリットを解説
▶関連コラム:【倒産防止共済】4つのメリットとは?利用前に確認しておきたいデメリットや注意点も解説
経費の計上による節税
2つ目は、備品や設備の購入による節税です。
青色申告で確定申告をしている事業者は、「少額減価償却資産の特例」によって、30万円までの資産を全額経費に計上できます。
(参考)国税庁 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
たとえば、パソコンやプリンターといった備品の購入で、今期の利益を抑えながら業務の効率化を図れます。
▶関連コラム:【確定申告の裏技5選】2月からでも間に合う節税方法とは?パソコンを償却資産として計上など
会計作業を効率化するツールを導入
3つ目は、確定申告にかかる事務負担を減らす工夫です。
たとえば、会計ソフトの導入や領収書用のスキャナーといった設備の導入によって、記帳や確定申告にかかる手間を減らせます。
電子帳簿保存またはe-Taxによる確定申告によって、青色申告特別控除の金額を増やすことも可能ですので、電子化していない方は導入を検討しましょう。

橋場先生
節税制度や電子化ツールは、制度理解や導入タイミングによって効果が大きく変わります。
「どの制度を使えばいいのか分からない」「確定申告をもっと楽にしたい」という方は、『お客様の貴重な資産と時間を守る』ARK税理士法人にご相談ください。
確定申告対策の注意点を確認
確定申告の節税制度や特例は魅力的ですが、適用条件やルールを誤ると「無効」になったり、税務調査で指摘を受けることもあります。
記事の終わりに、事前に押さえておきたい注意点の例を紹介します。
- 小規模企業共済は「会社員との兼業」では加入不可
- 倒産防止共済は「1年以上の事業継続」が必要
- 経費計上は「事業に直接必要な支出」に限られる
- 電子帳簿保存法のルールに沿ってデータ保存する必要がある
- 控除や特例は“併用できないケース”もあるため制度確認が必須 など
実際に、節税や効率的な確定申告処理を図る場合、このように様々な注意点があります。
個人では判断が難しいケースもありますので、気になる方はARK税理士法人までご相談ください。
まとめ
確定申告は「年に一度の作業」ではなく、日々の管理と早めの準備が成果を左右する業務です。
積立制度の活用や経費計上、会計ソフトやスキャナーによる効率化を組み合わせることで、節税効果を高めつつ作業時間も短縮できます。
ただし、共済の加入条件や経費計上の範囲、電子帳簿保存法などには細かなルールがあるため、自己判断だけで進めるのはリスクです。
正しく制度を理解し最適な方法を選ぶことで、余計な税負担を防ぎながら安定した経営につなげられます。
確定申告や節税対策で不安を感じたら、ぜひ税務のプロであるARK税理士法人へご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.