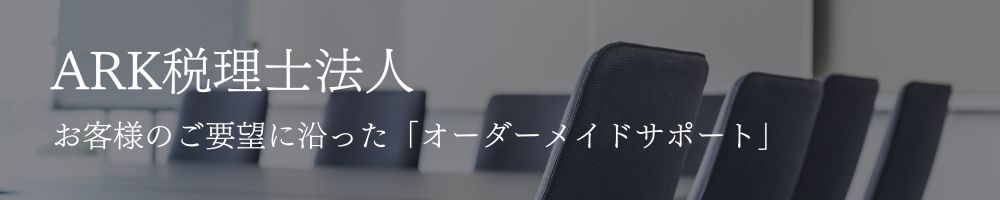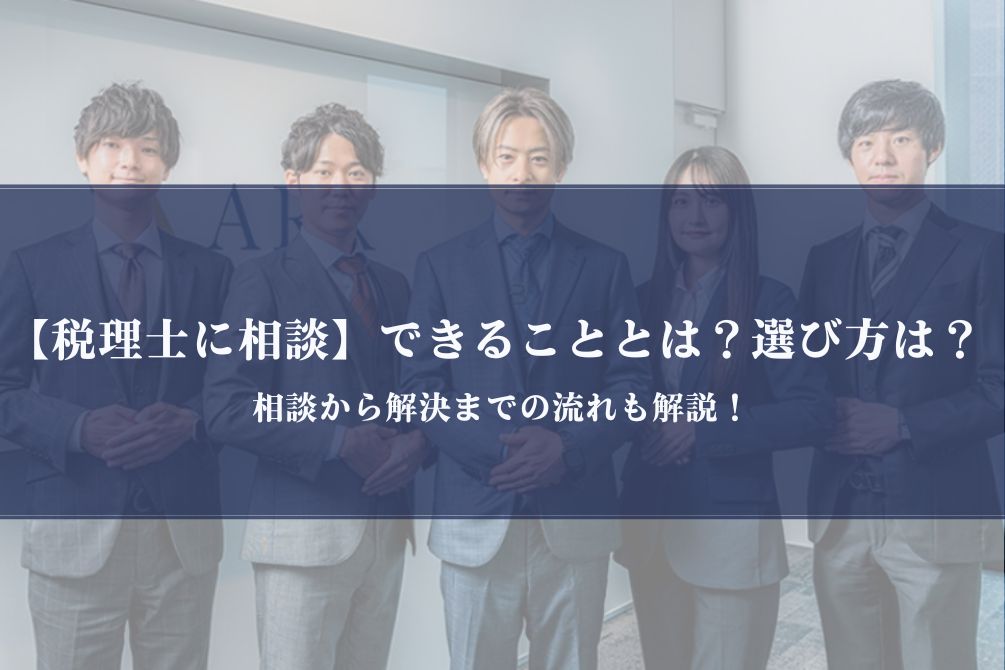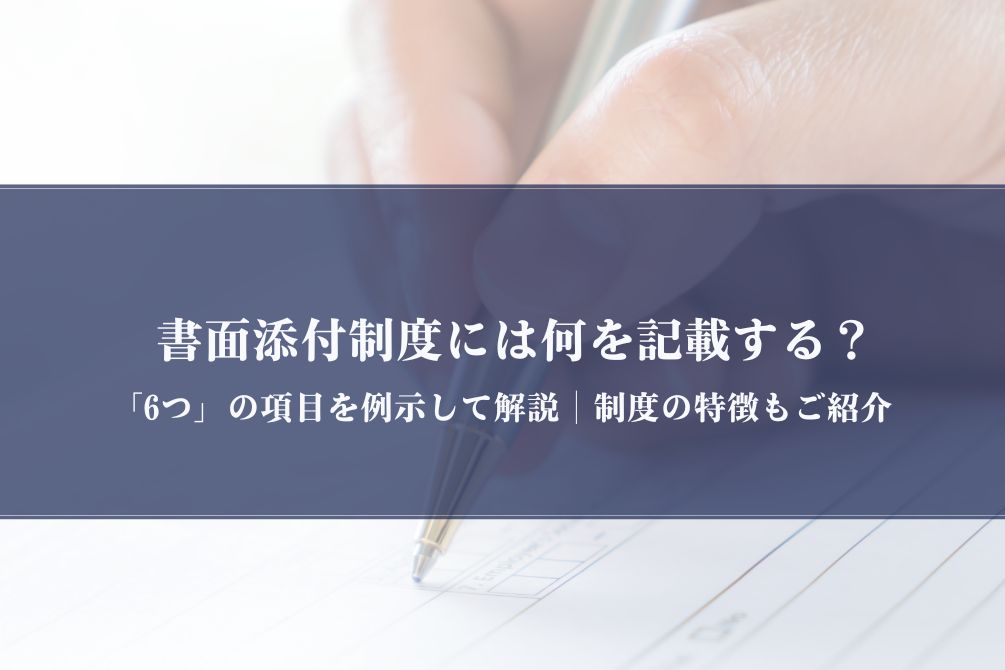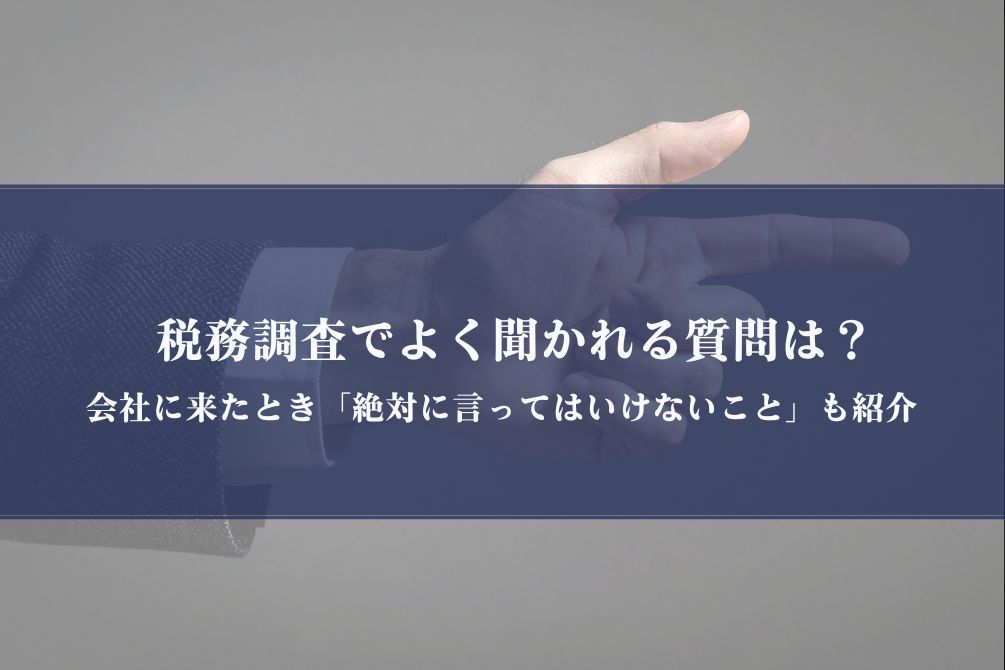【税金免除】実は”救済制度”あります!収入が減った時、税金を安くする方法を解説
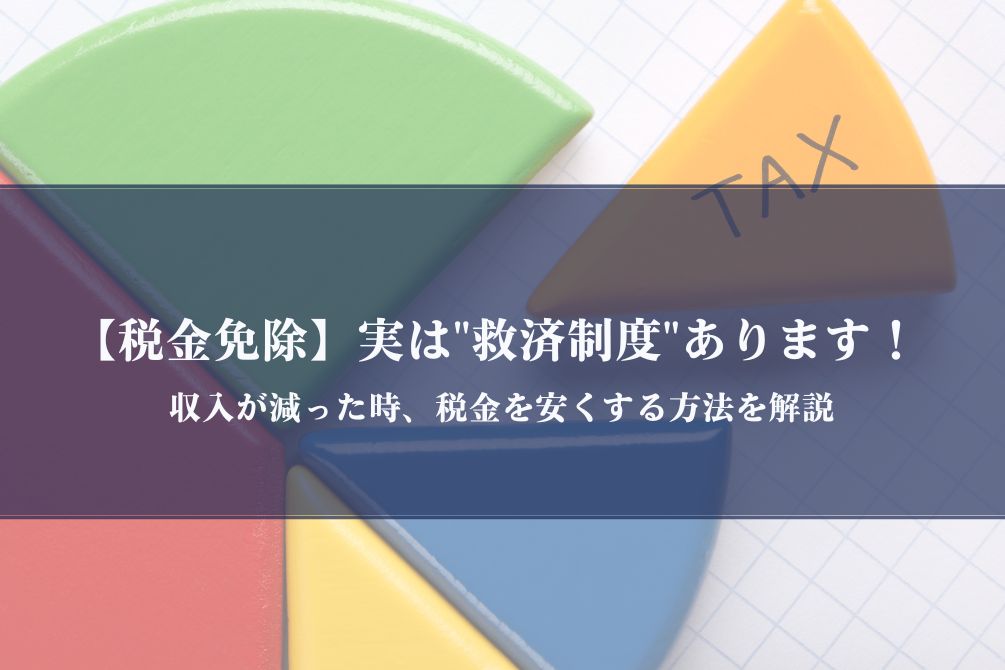
「退職して収入がゼロに」「フリーランスの仕事が激減した」
そんな状況でも、住民税や年金の請求書は例年通り届きます。
「収入が減った分、税金を安くする方法はないか」と疑問に感じることはありませんか?
実は、住民税、国民年金といった支払いは、条件を満たせば減税や支払い猶予の対象になることがあります。
たとえば、退職や失業、病気による休職といった理由で収入が大きく減少したとき、また事業の休止、廃止をした場合です。
本記事では、会社員と個人事業主それぞれが利用できる税金の減免・猶予制度をわかりやすく解説します。
制度の仕組みや注意点、申請のポイントを理解して、無理のない形で税負担を軽くしましょう。
目次
会社員・個人事業主別│利用できる税金の減免・猶予制度
収入が減少した場合など家計にとってピンチのとき、利用できる制度には、どのようなものがあるのでしょうか。
会社員の方と個人事業主の方に分けて、減免や猶予についての制度をご紹介します。
会社員が利用できる減免・猶予制度
会社員の方が利用できる、税金の減免・猶予制度の例としては、次の2つがあります。
個人住民税の猶予・減免
住民税は前年の所得を元に課税されますので、今年になり収入が大きく減少した場合でも、前年度の収入に基づいて税金が請求されます。
このとき利用できるのが、住民税の猶予や減免制度です。
- 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
- 本人もしくは本人と生計を一にする親族が、病気にかかったとき、または負傷したとき
- 事業を廃止したとき、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
こうした事情がある場合、申請することで猶予を受けられ、それでも支払いが困難な場合には減免を受けられる可能性があります。
(参考)中央区 納税が困難な方に対する地方税における猶予制度について
国民年金保険料の猶予・減免
住民税と同様に猶予や減免を受けられる可能性がある制度は、国民年金保険料の猶予・減免制度です。
本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、承認されると全額・4分の3・半額・4分の1、いずれかの割合まで免除を受けられます。
また、同様に前年所得が一定以下の場合に、保険料の納付猶予を受けられます。
(参考)日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
個人事業主が利用できる減免・猶予制度
個人事業主においても、会社員の方と同様に住民税や国民年金保険料の納付猶予や免除を受けられます。
そのほか、事業を営む方の場合は、厚生年金保険料について、「換価の猶予」または「納付の猶予」を受けられます。
- 換価の猶予:保険料などの分割納付が可能に
- 納付の猶予:保険料などの一定期間猶予を受けられる
こうした制度の利用によって、災害や雇い止めといった事態に直面した場合でも、支払いの免除や猶予を受けて経済的な負担を軽減することが可能です。
(参考)日本年金機構 厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)

橋場先生
万が一の際、こうした各種制度を冷静に調べて利用することは、実は困難です。
もしもの事態に経済的な観点から備えるためには、普段から税金の専門家との付き合いを持つことが重要です。
ご紹介した各種制度のほか、税金についてのあらゆる悩みは、ARK税理士法人にご相談ください。
どれくらい安くなる?具体的な効果を試算
収入が大きく落ちた年でも、適切な申請により猶予や減免が実行されると、経済的な負担が軽くなるケースがあります。
例として、国民年金や住民税の減免を受けた場合の、実際の数値をあてはめて節約効果を確認します。
【国民年金と住民税の軽減シミュレーション】
前年と比較して、収入が大幅に減少した場合に「国民年金の保険料の減免制度」と「住民税の減免制度」を利用したケース。
シミュレーションの前提条件
- 居住地:千葉県市川市
- 家族構成:本人、配偶者、高校生の子ども2人(16歳、17歳)
- 前年の年収:320万円
- 今年の年収:160万円(約半減)
国民年金(1/4免除の場合)
- 通常:月16,980円(年間203,760円)
- 免除後:月4,245円(年間50,940円)
- ▶年間152,820円の軽減
住民税(2割減税の場合)
- 本来の税額:32万円
- 減税後:25.6万円
- ▶年間64,000円
これらを合計すると、年間で約21万6,000円の負担減となります。
年金・税金の減免制度をうまく活用すれば、家計への影響を大きく抑えられることが分かります。

橋場先生
こうした制度の適用には、所得や家族構成に応じた細かな確認と、正しい申請手続きが必要です。
「自分が対象になるのか分からない」「手続きに不安がある」
そんなときは、専門家に相談すると安心です。
ARK税理士法人では、減税・猶予の申請サポートをはじめ、確定申告や資金対策も丁寧にご案内していますので、万が一に備えたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
減免・猶予制度利用についての注意点
こうした制度の利用には、一定の注意点もありますので、記事の終わりにご紹介します。
- 税金や保険料の減免・猶予制度は必ず申請が必要
- 申請時には前年の所得や世帯収入、保有資産の状況などの確認を求められることがある
- 制度によっては、毎年の更新や再申請をしないと失効するケースがある
- 国民年金の免除を受けた場合は、将来の年金額が減少する可能性がある(希望すれば10年以内の追納で補填することも可能)
▶関連コラム:年金額を増やす方法がある!?『追納』のメリットについて、税理士が詳しく解説
まとめ
収入が減ったときでも、申請を行うことで税金や保険料の負担を軽くできる制度が用意されています。
住民税や国民年金は、条件を満たせば一部または全額の減免・猶予が受けられる可能性もあり、万が一の際は制度を「知っているかどうか」で経済的な負担が変わります。
「自分が対象になるのか分からない」「いざというとき、適切に申請できる気がしない」といった方は、ぜひ専門家にご相談ください。
ARK税理士法人では、収入減少時の税務対応や申請手続きまで、丁寧にサポートいたします。
Contact
We will support you like a butler.