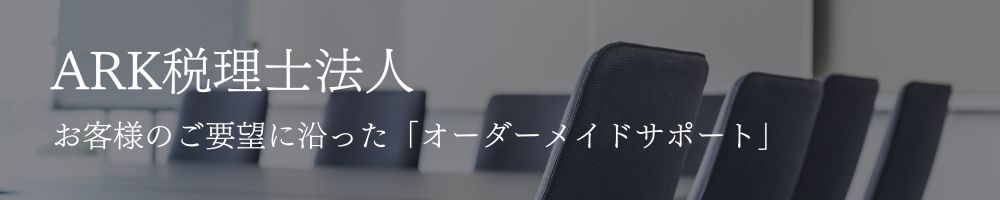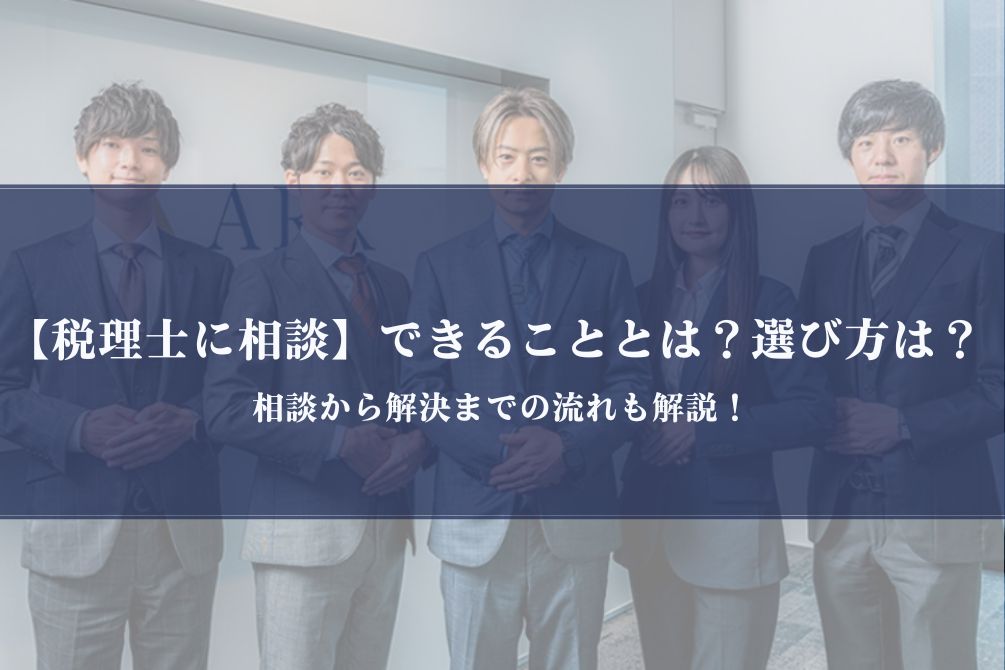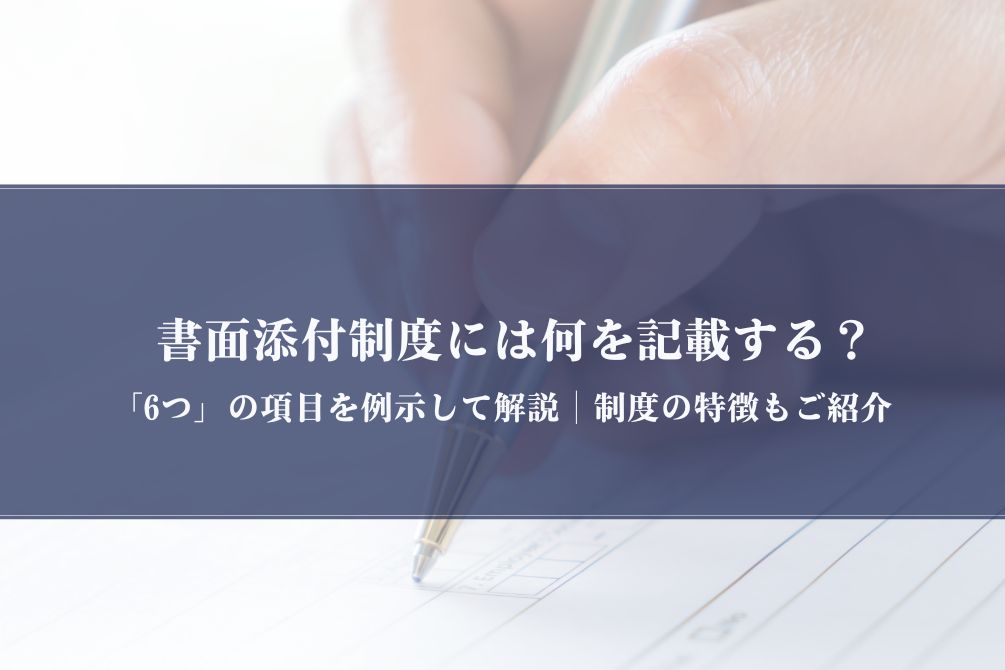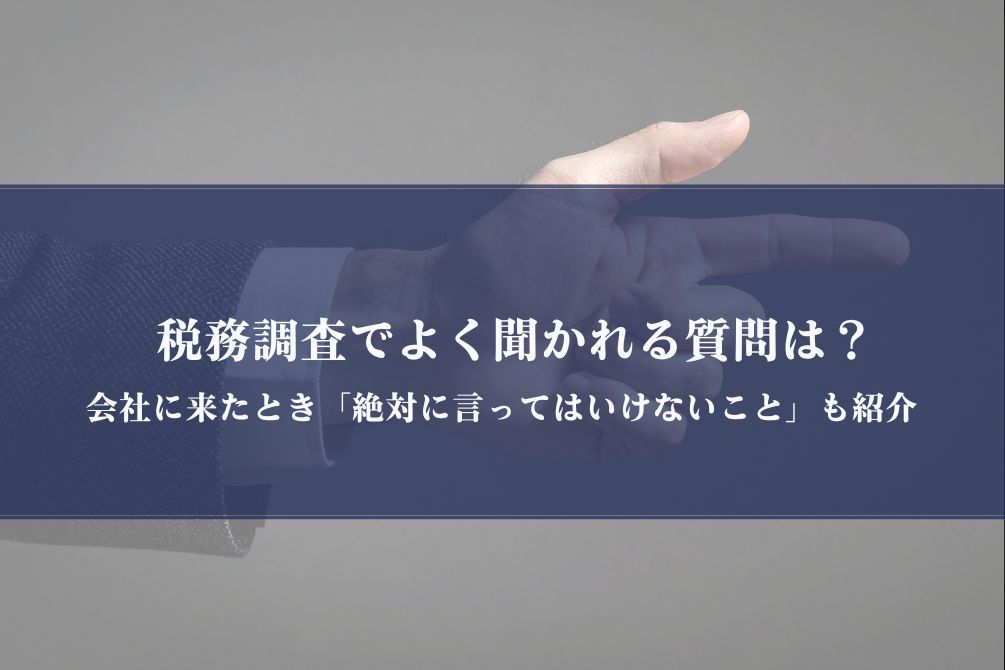【所得税の節税は『所得控除』から】今日から節税に使える「所得控除12選」をご紹介
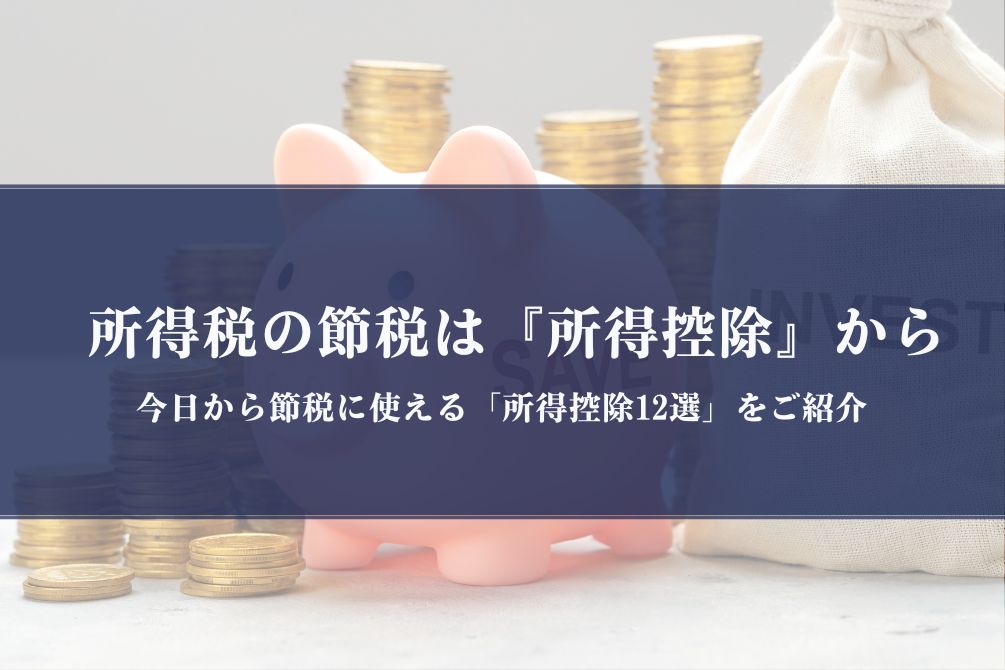
所得に応じて税金が課される「所得税」、節税する方法は複数ありますが、中でも効果が高いのは「所得控除」を利用することです。
医療費や保険料、ふるさと納税など、実は日常生活に直結している所得控除ですが、知らずに確定申告(年末調整)すると、控除を受けられず損をする可能性も。
本記事では、今日からでも利用したい代表的な12の所得控除について整理し、所得税を節税する方法を解説します。
目次
所得税の節税は「所得控除」の活用がカギ
所得に応じて金額が高くなる所得税は「課税所得×税率」で計算されます。
つまり、課税所得を小さくすることが、節税するためのポイントになるということです。
ここで役立つのが「所得控除」という仕組みです。
所得控除は、医療費や保険料、扶養家族の有無などに応じて一定額を課税所得から差し引くことができる制度で、所得税額を減らす効果があります。

橋場先生
所得控除は節税効果が高い一方で、制度の種類や適用条件が複雑で、申告漏れのリスクもあります。
確実に活用して税負担を抑えるためには、専門家によるサポートがおすすめです。
ARK税理士法人では、所得控除を含めた最適な節税対策をご提案していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
代表的な所得控除
所得税を節税するために、まず確認しておきたいものは「代表的な所得控除」です。
誰でも受けられるものから、保険などの支払い状況や”ふるさと納税”利用の有無などによって適用されるものまで幅広く存在します。
まずは基本となる8種類についてご紹介します。
(1)基礎控除
所得のある人すべてが利用できる、もっとも基本的な控除です。
- 対象者:すべての納税者
- 控除額:最大48万円
- 特記事項:所得2,400万円超で段階的に縮小、2,500万円超で適用不可。
(2)社会保険料控除
年金や健康保険など、生活に欠かせない社会保険料を支払った分を差し引ける制度です。
- 対象者:国民年金、厚生年金、健康保険、介護保険などを支払った人
- 控除額:支払った社会保険料の全額
- 特記事項:家族分を本人が負担している場合も対象。
(3)生命保険料控除
生命保険や個人年金の掛金に応じて、一定額を控除できる制度です。
- 対象者:生命保険、介護医療保険、個人年金保険などに加入している人
- 控除額:最大12万円(新契約)
- 特記事項:旧契約・新契約で上限額が異なる。
(4)地震保険料控除
地震保険に加入している場合に、保険料の一部を控除できる制度です。
- 対象者:地震保険料を支払っている人
- 控除額:最大5万円
- 特記事項:旧長期損害保険(経過契約)は最大15,000円。
(5)小規模企業共済等掛金控除
将来の退職金を積み立てながら、掛金を全額控除できる自営業者向け制度です。
- 対象者:個人事業主や中小企業経営者などで、共済に加入している人
- 控除額:掛金の全額
- 特記事項:節税と老後資金準備を両立。加入資格や限度額に注意。
▶関連コラム:【個人事業主の厚生年金の代わり】小規模企業共済、4つのメリット・2つのデメリットを解説
(6)医療費控除・セルフメディケーション税制
1年間の医療費が一定額を超えた場合や、市販薬の購入でも控除を受けられる制度です。
- 対象者:年間10万円以上(または所得の5%超)の医療費を支払った人/対象市販薬を購入した人
- 控除額:(医療費控除)支払額−10万円 (セルフメディケーション税制)上限8.8万円
- 特記事項:家族分を合算可能。領収書や明細書の保存が必須。
(7)寄附金控除(ふるさと納税を含む)
自治体やNPO法人への寄附が節税につながる制度で、ふるさと納税も含まれます。
- 対象者:認定NPO法人や自治体などに寄附した人
- 控除額:寄附額−2,000円(所得に応じた上限あり)
- 特記事項:ふるさと納税は実質自己負担2,000円。
▶関連コラム:【個人事業主必見】ふるさと納税は結局お得なのか?年収シミュレーションで解説
(8)雑損控除
災害や盗難、火災など不測の事態で損害を受けた際に利用できる控除です。
- 対象者:自然災害・盗難・火災などで損害を受けた人
- 控除額:損失額 − 総所得金額の10%、または(損失額 − 保険補填金 − 5万円)のいずれか大きい金額
- 特記事項:特定のケースのみ適用。証明書や資料の提出が必要。

橋場先生
ご覧のとおり、所得控除にはさまざまな種類があり、それぞれ条件や控除額が異なります。
どの制度をどのように活用できるかを正しく判断するには専門的な知識が必要です。
ARK税理士法人では、お客様の状況に合わせた最適な節税プランをご提案していますので、安心してご相談ください。
家族構成に応じた所得控除
所得控除の中には、家族の有無や生活状況によって適用されるものがあります。
扶養家族や配偶者の所得状況、障害の有無、学生であるかどうかなどによって控除額が変わるため、状況に応じて確認することが大切です。
(9)扶養控除
子どもや両親などを扶養している場合に適用される控除です。
- 対象者:16歳以上の子や両親を扶養している人
- 控除額:一般扶養で38万円/特定扶養(19歳以上23歳未満)63万円/老人扶養48万円〜58万円
- 特記事項:同居と別居、年齢によって控除額が異なる。16歳未満の子どもは児童手当対象のため控除なし。
(10)配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の所得が一定以下の場合に適用される控除です。
- 対象者:配偶者控除(配偶者の所得が48万円以下の場合) 配偶者特別控除(48万円超〜133万円以下の場合)
- 控除額:配偶者控除(最大38万円) 配偶者特別控除(1〜38万円、所得に応じて段階的に変動)
- 特記事項:納税者本人の所得が一定額を超えると適用外。計算が複雑なため申告漏れに注意。
(11)障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除
生活上の事情を考慮し、税負担を軽減する控除です。
- 対象者:
(障害者控除)障害者本人または扶養親族が障害者
(寡婦控除)配偶者と離婚・死別した寡婦
(ひとり親控除)ひとり親として子を養育している人 - 控除額:
(障害者控除)27万円・40万円・75万円(区分による)
(寡婦控除)27万円
(ひとり親控除)35万円 - 特記事項:重度障害や同居の有無で金額が変わる。寡婦控除は年収制限あり。
(12)勤労学生控除
学生が働きながら学ぶ場合に適用される控除です。
- 対象者:勤労収入がある学生(合計所得75万円以下が条件)
- 控除額:27万円
- 特記事項:アルバイトやパート収入が対象。学業を本分としていることが前提。
まとめ
所得控除は、誰もが受けられるものから、家族構成や生活状況によって適用されるものまで幅広く存在します。
適切に活用すれば、所得税の負担を数万円〜数十万円単位で減らすことも可能です。
ただし、制度ごとに条件や控除額が細かく異なるため、申告漏れや計算ミスのリスクもあります。
確実に節税を実現するためには、専門家のサポートを受けると安心です。
ARK税理士法人では、最新の税制に基づいた節税対策や確定申告のサポートを行っています。
「自分はどの控除を使えるのか?」と悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.