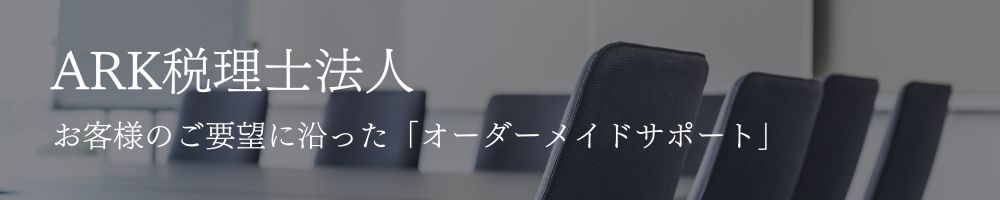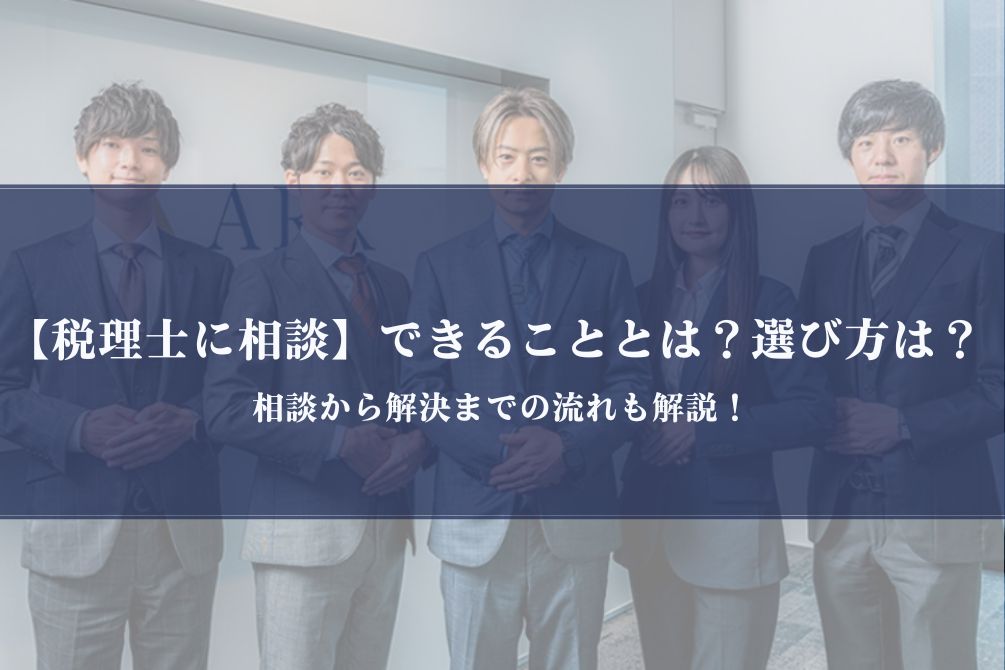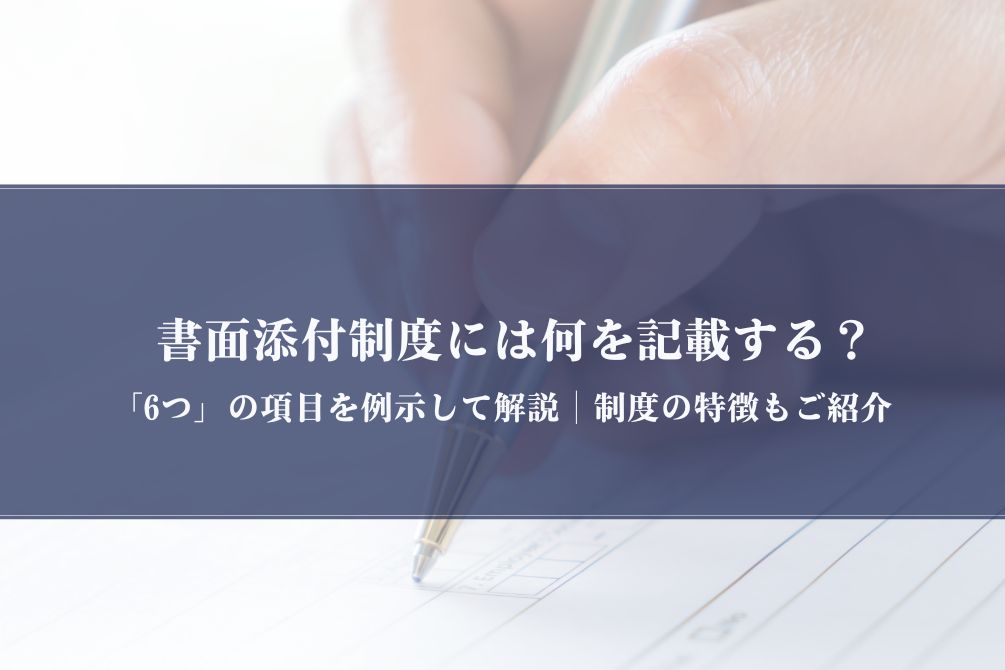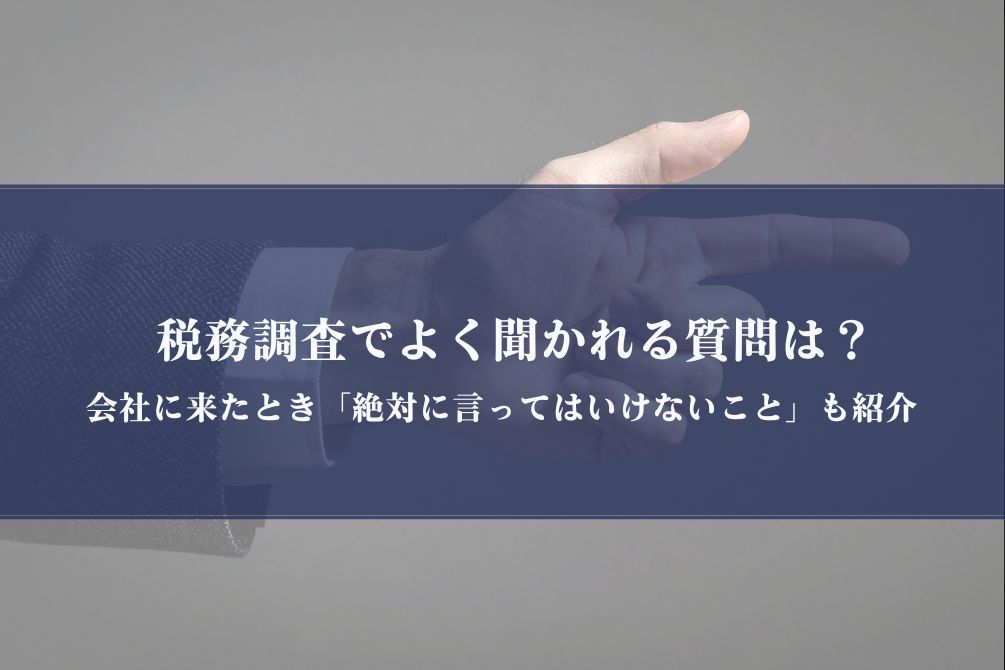【今期売上が上がった方へ】来年の支払いを経費にして節税できる!制度と注意点を解説
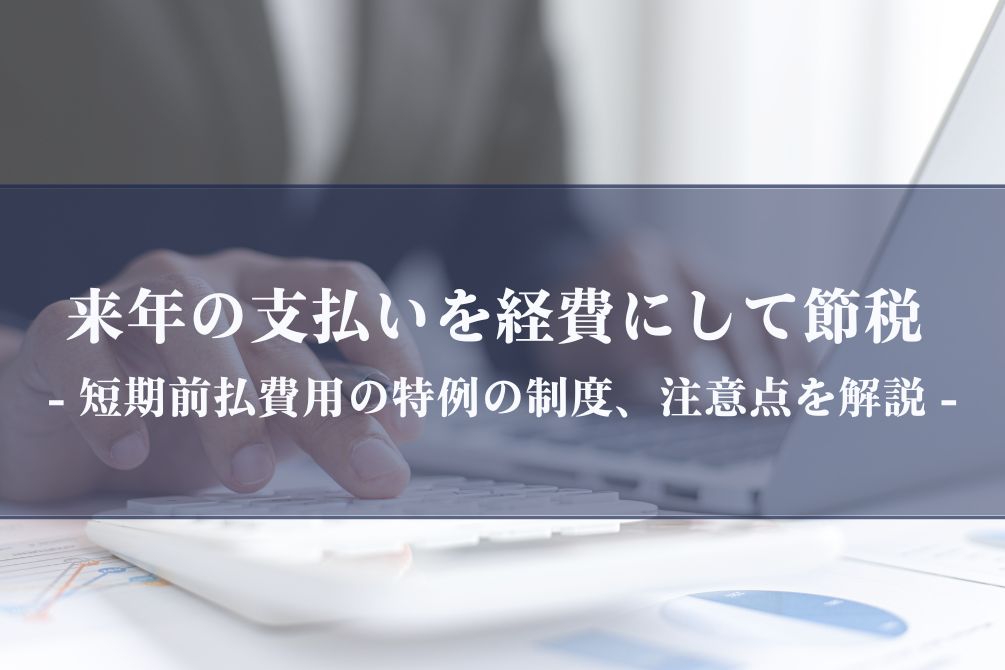
事業を営む方の中には「売上が好調で、税金を抑える方法を知りたい」と考える方もいるでしょう。
節税する方法のひとつは「短期前払費用の特例」を利用して、家賃などを経費として計上することです。
本記事では、短期前払費用の特例について制度の概要を紹介するとともに、経費として計上できる費用の例や経費として満たす必要がある要件や注意点についても解説します。
国が設けているこうした制度を上手に活用して節税し、手元に残る収益を増やしましょう。
目次
翌年分の経費を当年度計上する「短期前払費用の特例」とは?
短期前払費用の特例とは、国税庁のホームページでは次のように記載されています。
前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
つまり一定の条件を満たすことで、前払費用として支払った費用について、翌年度の費用を当年度の費用として計上できる制度ということです。
利用できる経費の種類
具体的に、利用できる経費の種類には、次のような例が挙げられます。
利用できる経費の例
- 土地、建物の賃料
- システムのリース料
- サーバー使用料
- 物を借りて支払うレンタル料、リース料
- 生命保険料、火災保険料など
- 雑誌の年間購読料(電子版)
利用できない経費の例
- 固定資産の購入代金(社用車や機械設備の導入費など)
- 雑誌の年間購読料(電子版を除く)
- 単発の広告掲載料
- 1年を超える長期契約のリース料

橋場先生
より詳しく、どういった費目が対象になるのか確認したい方、制度について知りたい方はARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
短期前払費用の特例の要件や注意点を確認
前の章で紹介したように、短期前払費用の特例には利用できる経費と利用できない経費があります。
制度利用の可否を確かめるために、具体的な要件を確認しましょう。
- 毎月変わらないサービス内容
- 支払ってから1年以内に受けるサービス
- 決算締日にまでに支払うこと
- 継続して支払っていくこと
- 支払った経費から売上が発生しないこと
毎月変わらないサービス内容
1つ目は、毎月変わらない内容のサービスを対象とすることです。
短期前払費用の特例は「等質・等量の役務」に対するものである必要があります。
家賃や保険料など、毎月内容や分量が変わらないサービスに対してのみ特例を利用できます。
たとえば、ウェブ媒体での雑誌は対象となる一方で、紙面としての雑誌や新聞は対象外となりますので注意が必要です。
支払ってから1年以内に受けるサービス
2つ目は、支払ってから1年以内に受けるサービスであることです。
「短期前払費用」の定義の中に「1年以内に提供を受ける役務」とあるとおり、本制度は短い将来のサービスを対象としています。
1年を超える先が対象となる前払いは対象外となります。
決算締日までに支払うこと
3つ目は、決算締日までに支払うことです。
本制度は支払った費用を当年度の損金として計上します。
このため支払いが決算日をまたぐ場合は、特例が適用されない可能性があります。
継続して支払っていくこと
4つ目は、継続して支払いを続けることです。
本制度は継続的な支払いが前提となる点に注意が必要です。
利益が出た年だけまとめて支払いをする、といった方法で本制度使う場合、利益操作として税務署より指摘を受ける可能性があります。
なお、「継続的」について明確な決まりはないものの、おおむね3年以上継続することを目安としましょう。
支払った経費から売上が発生しないこと
5つ目は、支払った経費から売り上げが発生しないことです。
たとえば、本制度を利用して借りた土地や建物、車などを又貸しして利益を得る行為は本制度の目的に反します。
こうした利用法を防ぐために、本制度を活用した経費から売り上げが発生することは認められません。

橋場先生
こうした注意点を知りたい方もARK税理士法人まで、お気軽にご相談ください。
まとめ:短期前払費用の特例を上手に活用する
翌年の支払いを当年の経費として繰り入れて節税を図れる、短期前払費用の特例について解説しました。
こうした制度を活用することで、売り上げの多い年であっても十分な経費を計上でき、納税額を抑えられる可能性が高まります。
本制度の内容や注意点、またその他の節税策についても詳しく聞きたい方は、ARK税理士法人までお気軽にご相談ください。
Contact
We will support you like a butler.